
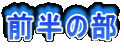 |
| 4: ���k�x���@�H�c�����\�@�H�c�s���R�����w�Z ���� �i�w��:�ؓ��P�j4�N�A��33��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�o���G���y�u�O�p�X�q�v���@�����̗x��A�I���̗x���iM.�t�@�����^�V�쐳���j�q�Ȃ������ԉ��܂��ė����̂��A���ɃN���A�ȃT�E���h�����ɋ����킽��܂����B���̑��݊��͔��Ɏ������o���h�ł����A�S�̂�ʂ��āA���j�]���̐��x���Â��A�S�̂̃o�����X�I�ɂ��u�����h�����������Ȃ������̂��c�O�ł��B�}�[�`�Ƃ��Ă��A6/8�̃��Y�����s����ŁA�I�n�����Ȃ�����ɂȂ��Ă��܂��܂����B���R�Ȃ́A���N�̐��t�y�t�@���Ȃ�A��C��1975�N�Ƀ^�C���X���b�v߂��Ă��܂������Ȑ��ȑI�Ȃł��B�ۑ�ȂƔ�r����ƁA����I�ɃT�E���h�̃o�����X���A�A���T���u���̐��x�����̃��x���������グ�Ă��܂����B���ɒ��Ոȍ~�́A�����W�̍L���T�E���h�Ɩ����������ς��̉��y�Ƃ̃R���{���[�V�������A�����ȉ��w�������N�����Ă��܂����B�e�q���ŁA�����y�Ȃɂ����܂���܂��܂������A���̎���Ȃ�ł͂̓V�쎁�̌����ȃI�[�P�X�g���[�V�������A��Y���Ă��܂����B |
| 8: ���֓��x���@��t����\�@���ˎs����ꒆ�w�Z ���� �i�w��:���؍K�G�j���o�� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:���t�y�̂��߂̕��i���u�z������Ƃ��v����i�������j���ɃN���A�ȃT�E���h���苿���Ă����ۑ�Ȃ̃C���g���ł������A�T�E���h�S�̂Ƃ��ău�����g��������ɗ~�������ȂƂ�����ۂł����B�������A�X�̑t�҂̉��t�͍͂����A�k���ȃA���T���u�����S�n�悢�}�[�`�Ɏd�オ���Ă��܂����B����Ȓ��ŁA�`���[�o�����ܔ����~�X�������Ă����̂͐ɂ��������Ǝv���܂��B���R�Ȃł́A�S���ʂ̐��E�ς����グ��̂ɐ������Ă��܂����B�G�b�W�̂���T�E���h�����̊y�ȂɃ}�b�`���Ă��āA���x�̍����A���T���u����������㉟�����Ă����悤�Ɋ�����ꂽ�̂��A���w���Ƃ��Ă͋����ł����B��������������ƍۗ����A�S�̂̉��y�����k���ʼnf���I�ł������A�����ł����ܔƂ��Ă��܂������~�X���c�O�ł����B�T�E���h�̃n�����X�����A���ɁA�ቹ���Ɋւ��āA�ׂ����z�����Ăق������������ł��B |
| 9: ���C�x���@�O�d�����\�@�鎭�s�����q���w�Z ���� �i�w��:���R���ق�j���o�� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�̌��u���X�v�l�v�Z���N�V�����iG.�v�b�`�[�j�^�勴�W��j���ɂ悭�u�����h���ꂽ�T�E���h����X�^�[�g�����ۑ�Ȃ́A���̃n�[���j�[�̏d�˕��ȂǁA���N�����Ă����ۑ��4�Ԃ̒��ł��A�G��̃A�i���[�[���{���ꂽ�G���ł����B�����}�[�`���̂��̂͂��d�߂ȃC���[�W�ŁA�����ŃA���T���u�������ꂽ��A�����~�X���U�����ꂽ�̂��c�O�ł��B���R�Ȃ́A�`���������j�]���̐��x���Â��������܂������A���̌�͍������x���������A���T���u���ƁA�d���ȃT�E���h���y�ȂɃ}�b�`�����D���ɂȂ�܂����B�I�Ղł̓T�E���h�ɉ�����������A�����I�ȃN���C�}�b�N�X�ւƉ��S�̂��̂ɐ������Ă��܂����B�����A�ቹ�Z�N�V�����A�o�X�g��������Ŕj�����܂Ŋ���o���Ă����̂��A�l�I�ȍD�݂Ƃ��ẮA���c�O���������ȂƎv���܂��B�������A�Ō�܂ŏW���͂�炳�Ȃ��t�҂̉��y�͂͌����ł����I |
| 10: ���֓��x���@���ʌ���\�@�������s���ݒ��w�Z ���� �i�w��:����x�q�j2�N�Ԃ�3��� �ۑ��3:�u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j ���R��:�̌��u��̋R�m�v�g�Ȃ���i�q.�V���g���E�X�^���q���j���Ɉ��肵���n�[���j�[�����C���g������X�^�[�g�����ۑ�Ȃ́A�������ۗ������A�y�Ȃ̐��E�ς����܂��Č������D���ł����B�A���T���u�����k���ŁA�o�����X���悭�����Ă��܂������A�����~�X���U�����ꂽ�̂��A�c�O�Ƃ����Ύc�O�B�X�l�A�̃`���[�j���O�����̊y�Ȃɂ́A����a���������܂����B���R�Ȃ͗E�s�ȃz��������X�^�[�g���܂����A�����ɂ͂�萳�m�������߂����Ƃ���ł��傤���B���̌�́A�����W�̍L���T�E���h���S�n�悭�y�Ȃ̐��E�ς��Č����Ă��܂������A�n�[���j�[�ɑ����̃u��������ꂽ��A������������Ă��܂��ȂǁA���y����╽�R�ɂȂ��Ă��܂��Ă����̂��c�O�ł����B�����O�̃_�C�i�~�b�N�ȃT�E���h�����A�X�Ȃ�X�L���A�b�v�Ɋ��҂������Ƃ���ł��B |
| 14: ���֓��x���@��t�����\�@���ˎs����l���w�Z ���� �i�w��:�{�������j2�N�A��6��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�������́`�O�̈قȂ�\���Ł`�i�������j�ۑ�Ȃ̃C���g���ɂ�����I�[�P�X�g���[�V�����́A��͂肱�̕S��B���̃o���h�ł���J���Ă���悤�ł����B�������A�o�����X�̂悢�N���A�ȃT�E���h�́A����܂ł̗���@����悤�ȑ��݊��ŁA�A���T���u���̐��x�������G���ł����B�����}�[�`�Ƃ��ẮA���`���[�o�̍��ݓ��A���Y���̗��ꂪ��؋C�������������m��܂���B�I�Ղ̖؊ǂׂ̍����p�b�Z�[�W�̐��������͂������ł��B���R�Ȃ́A���N���s���1�ȂɂȂ�܂����ˁB�o���_�͂��̃o���h�ɂ��Ă̓X�e�[�W�O���ōs���Ă��܂������A���̃o���h�Ɠ������A����ōs���������A���y�̃u�����h���Ƃ��Ă͌��ʓI�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B���̌�́A�k���ȃA���T���u���ƁA�X�̑t�҂̉��t�͂��������x���ō��̂����D���ŁA�w���҂��o���h�̉��F�Ɖ��ʂ����݂ɑ����Ă��邩�̂悤�ȍ��o���o����قǂ̉��y�͂̍������������Ă��܂����B |
| 1: ���x���@���Ɍ���\�@���Ð�s���l�̋{���w�Z ��� �i�w��:�����~�q�j3�N�A��7��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�����̌��̋P�{���i�M���듿�j�ۑ��Ȃ́A6/�W�̍��݂��S�n�悢�C���g������X�^�[�g���܂����B�����A����Ԃ̏o��������Ȃ̂��A�S�̓I�ɒ���̊y�킪�o�����X�I�Ɏ�߂ŁA�ቹ�Ɛ����ƃ��Y���������ۗ��A�o�����X�̈����T�E���h�ɂȂ��Ă��܂����̂��A�c�O�ł����B�s�b�`��n�[���j�[�͈��肵�Ă��܂������A�S�̂̃u�����h������܈�ŁA�I�Ղ̓g�����{�[������≹�ʉߑ����ȂƂ�����ۂŁA�z�[���̋�C�̗���ɂ��܂����y������Ȃ����������ł��B���R�Ȃ́A�j�q���k�ɂ��a����5�l�g���D�u�Ƃ����p�t�H�[�}���X��i�����D���ł������A�T�E���h�ɍX�ɉ����~�����������ȂƂ����̂ƁA�ቹ�y�킪����߂ŁA�S�̂̃o�����X�Ƃ��Ă��A�����������ꂪ���ɂȂ��Ă��܂����B��͂蒩��ԂƂ����̂́A���w�̗̑͂ł́A�Ȃ��Ȃ����킷�鎖������悤�ł��B |
| 2: �����x���@�����s��\�@�����s��������O���w�Z ��� �i�w��:�V��N�G�j2�N�Ԃ�10��� �ۑ��3: �u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j ���R��:�t�@���g���E�h�D�E�����[���|���e�|�i�V�쐳���j�C���g���͂��n�[���j�[�������Ă��܂����ł��傤���B���̌�͐������ۗ������o�����X�̂Ƃꂽ�D���ł������A��┭���~�X���ڗ����Ă����̂��A�c�O�B�܂��A���X��l�̐F�C��t���߂��������m��܂���B���R�Ȃ́A�y�Ȃ̐��E�ς�I�m�ɍČ����A�����ȃT�E���h���悭�}�b�`�����D���ł����B����Ȓ��ŁA�ቹ�y��A���Ƀ`���[�o�͂��A�N���A�Ȕ��������߂��������Ƃ���ł��BSAX�Z�N�V�����̃A���T���u����A�t���[�g�A2�l�̃I�[�{�G�t�҂̉��t�͗���ŁA�����y��ɁA���NJy����ǂ����₩�Ƀu�����h�����邩�A���̕ӂ肪����̉ۑ�ƂȂ肻���ł��B���t�͂��̂��̂͂��Ƃ��ƍ����o���h�Ȃ̂ŁA���_�͂����ɃN���A���ė��邾�낤�Ɗ��҂��Ă��܂��B |
| 11: ���C�x���@�É������\�@�l���s���J�����w�Z ��� �i�w��:�����K���Y�j2�N�A��2��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�C�[�X�g�R�[�X�g�̕��i�iN.�w�X�j���A�ȃT�E���h����X�^�[�g�����ۑ�Ȃ͎��̃��j�]���̐��x���Â��A���ǂƖ؊ǂ̃o�����X���������炩�A���œ_���ڂ₯�����y�ɂȂ��Ă��܂����B����Ȓ��ŁA�}�[�`�̃��Y����I�m�Ɉ����������Ŋy��Z�b�V�����̉��y�I�ȃp�t�H�[�}���X���D��ۂł����B�S�̂�ʂ��āA���ɋ��ǂ̔����~�X���ڗ������͎̂c�O�ł��B���R�Ȃ́A���Ղ̖L���Ȗ؊ǂ̋������S�n�悢���E�ς�����Ă��܂������A��������A�ׂ����p�b�Z�[�W�𑵂��Ăق��������Ƃ���ł��B�������A���̕ӂ肩��T�E���h�����悭�u�����h����A�L�т̂��鍂���u���X�̃T�E���h�����ʓI�ɉ��y�ɐF�ʊ��������炵�Ă��܂����B���Y���������悭�A�A���T���u������������������R�Ȃ̏[���Ԃ肪��ۓI�ł����B���ɁA���Ղ̃g�����y�b�g�\���̉��F�̔������ɂ͐S�����v�������܂����B |
| 12: �����x���@�L������\�@�L���s���������w�Z ��� (�w��:���c�����j2�N�A��2��� �ۑ��1: �ʼnʂĂ̏�̃[�r�A�i�����p��j ���R��:�E�C���h�I�[�P�X�g���̂��߂̃}�C���h�X�P�[�v�i�������j���N������ʂ��ĉ��t�����p�x�̏��Ȃ������ۑ��1�ԁB���Ղ���悭�������ꂽ�A�X�̉��t�͂̍������y�����܂����B���Ƀ��j�]���̐��x�������A�S�̂�ʂ��Ă��A���T���u�������肵���G���������Ǝv���܂��B���Ŋy�킪�o�����X�I�ɋ��������ł��傤���B���̕��NJy�킪�S�̓I�ɂ��ƂȂ��߂ɕ������Ă��܂��Ă����̂��c�O�ł����B���R�Ȃɂ����Ă��A���x�̍����A���T���u���͌��݂ŁA�o�����X�̂����T�E���h�����܂��āA���ΓI�Ɏ��̍������y�����������Ă��܂����B�����A�S�̂�ʂ��āA���y����₠������ڂŁA�R���g���X�g�̕t�����̍H�v��A�W���͂�ۂ������y�̎����͂�A���y�I�ȉ����̋����݂����Ȏ咣���~���������Ƃ���ł��B�������A�����ĉ��y�͂̍����o�����X�̎�ꂽ�D���������Ǝv���܂��B |
| 15: �k���x���@���䌧��\�@�I�]�s�������w�Z ��� �i�w��:���X�ؘa�j�j18�N�Ԃ�2��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�M���`���l�T���X�̌���i��؉p�j�j�N���A�ȃT�E���h�ŃX�^�[�g�����}�[�`�ł������A�T�E���h�͑S�̓I�ɉ����Ȃ��A�܂�6/8�̃��Y�����d���A�ɂ��}�[�`�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���̃o���h�����x�߂̃e���|�ݒ�ł������A���̃e���|�Ȃ�A����Ƀ^�C�g�ȃT�E���h�Ɖ��y��������A�v���[�`���~���������Ƃ���ł��B���R�Ȃ́A�S�̂�ʂ��āA�S�Ẳ��y�̗v�f���荇���Ă銴���ŁA���y�I�Ȑ������܂��܂��K�v�������̂ł͂Ȃ����ȂƂ�����ۂł����B�Ŋy��̃o�����X�����������y�Ȃɂ����Ă͂���ɋC�������ė~���������Ƃ���ł��B�S�̓I�ɌX�̑t�҂̉��t�͍͂����Ƃ�����ۂł������A���������f�ނ��ǂ��������̂��A�S�����ɂ����Ă͂��������A�v���[�`�����߂��鎖�ł��傤�B |
| 3: �k�C���x���@���ْn���\�@���َs���ˑq���w�Z ���� �i�w��:���R�T�K�j���o�� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�̌��u���X�v�l�v����iG.�v�b�`�[�j�^�ʎ蓹�j�j�ۑ�Ȃ̃C���g���́A�T�E���h�����Ƀ��A�ŁA�s�p�I�ɂ��X�g���[�g�ɋq�Ȃɓ`����ė��܂����B�S�̂̃o�����X�����܂ЂƂŁA6/8�̃}�[�`�̃��Y��������؋C���������ł��傤���B�y�ȑS�̂Ƃ��Ă��A�X�Ȃ�A�i���[�[�̗]�n������悤�Ɋ����܂����B��ʂ��Ƃ̃����n�����s���������ŁA�I�Ղ̓A���T���u��������A�G�R�Ƃ������y�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���R�Ȃ́A�`���̑����p�b�Z�[�W�́A��荂�����x�ō��킹�ė~�������ȂƂ�����ۂł����B�S�̂Ƃ��ẮA���y�̗�����悭�͂�ł��܂������A�A���A�̉��y�\���ȂǁA�܂��܂����y�I�ɒNj��ł���]�n�͂������悤�ȋC�����܂��B�܂��A�����ł���ʂ��Ƃ̃T�E���h�̌��I�ȕω����A���y�Ƀ����n�����~���������Ƃ���ł��B |
| 5: ���֓��x���@��ʌ���\�@����s���_�����w�Z ���� �i�w��:���쐴��j���o�� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�O�̃W���|�j�X���i�^���r�v�j�ۑ�Ȃ̃C���g���͂��G�R�ƂȂ�A���̌�̃}�[�`�ɓ����Ă��A�A���T���u�������肹���A�I�n�d�߂̃}�[�`�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�܂��������̃s�b�`�������A�T�E���h�Ƃ��Ă��I�n�Â����͋C�ƂȂ�A�����~�X���U������܂����B�܂��}�[�`�Ƃ����J�e�S���[�ł́A�X�l�A�̃T�E���h���ɂ���l�̗]�n���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���R�Ȃ́A�a�̐��E�ς����o���ɂ͓����Ă��܂���ł������A�f���I�ȕ\���͂��S�n�悢����Ԃ����o���Ă��܂����B�����A�����ł��\���y��̃s�b�`���s����v�f�͑����A���Ƃ��e�B���p�j�̃}���b�g�̑I�ѕ��ЂƂ���Ă��A�������r�̗]�n�͂܂��܂��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���Ոȍ~�͎��������āA�T�E���h�≹�y���{�̂����n�߂������ł͂���܂����B |
| 6: ���k�x���@���������\�@�쑊�n�s��������ꒆ�w�Z ���� �i�w��:�����a��j2�N�A��7��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�������u�h���E�t�@���v�iR.�V���g���E�X�^�X�c��_�j�ۑ�Ȃ́A�C���g�����特��������A�}�[�`�̗���������d�����y�ɂȂ��Ă��܂��܂����B��ʂ��Ƃ̃����n��������Ȃ������悤�ł��B�܂����܁A���y����דI�ɂȂ��Ă��܂��̂��A�}�[�`�Ƃ����J�e�S���[�̒��ɂ����ẮA���X��a���������܂����B���āA�ۑ�Ȃɂ����Ă͏d���Ɗ������T�E���h�����R�Ȃł́A���̑g�ݍ��킹�̖����A���R�Ȃł̓V���g���E�X�̐��E�ς�I�m�ɕ\������̂ɐ������Ă��܂����B�����A�����p�b�Z�[�W��t�_�����̊������ȂǁA�����������y�ł͌������Ȃ��k���ȃA���T���u���ɂ͂�≓���A�Z�p�I�Ȍ��r���]�܂��Ƃ���ł��傤�B�܂���t�����ł̈��芴���|���Ăق����Ƃ���ł��B�������A�ۑ�ȂƎ��R�Ȃŕʃo���h�̂悤�ȕϐg�Ԃ�ɂ͋�������A�I�ՁA���R�ŗ��̓I�ȉ��y���\�z����čs���̂ɁA�r�b�N���������܂����B |
| 7: �l���x���@���Q����\�@���R�s���쒆�w�Z ���� �i�w��:�����b���j4�N����9��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�����t���@�C�I�����̂��߂̃p���e�B�[�^��2�Ԃ��@�V���R���k�iJ.S.�o�b�n�^�X�c��_�j�ۑ�Ȃ́A�D�u�Ƃ����C���g���ƑO�i�͂̂���}�[�`���S�n�悩�����̂ł����A�T�E���h���S�̂�ʂ��ă��A�ŁA���y���I�n�G�R�Ƃ��Ă��܂��Ă����̂��c�O�ł����B�S�̗̂���Ƃ��Ă��A���������ł͂Ȃ��A�ׂ������y�\���̑g�ݗ��ĂɎ��Ԃ������Ď��g��łق����Ƃ���ł��B���R�Ȃ́A�`�������œ�������킸�A�ْ�������C�Ɋɂ�ł��܂��܂����B�S�̂�ʂ��Ă��A���y�����R�ŁA�t�҂͍������t�͂������Ȃ���A���ɖܑ̂Ȃ��ȂƂ�����ۂ��܂����B����Ȓ��ł��A���R�Ȃł̓n�[���j�[�ɂ����芴�������A�I�Ղ͐S�n�悢�g�D�b�e�B�̉��V���y���߂܂����B |
| 13: ��B�x���@�{�茧���\�@�{��s���嗄���w�Z ���� �i�w��:�����O�j29�N�Ԃ�4��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�E�C���h�I�[�P�X�g���̂��߂̃}�C���h�X�P�[�v�i�������j�ۑ�Ȃ͖`������W���͂������������ŁA�S�̂�ʂ��Ă��d���}�[�`�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�T�E���h���̂��̂̓o�����X�̂Ƃꂽ���������̂������Ă��܂����A�}�[�`�Ƃ����J�e�S���[�̒��ɂ����ẮA�G�b�W�̂��镔����A���y�I�ȑO�i�͂����߂���Ƃ���ł��傤�B���R�ȂɂȂ��Ă��A���̃T�E���h�J���[�͕ς�炸��F�ŁA�����ɉ��y��i�߂Ă������Ƃ��������ł������A1�Ȃ̒��ŁA��ʂ��ƂɐF�ʊ���ς��铙�̍H�v����͂�~�����Ƃ���ł��B�A���T���u���ɂ����Ă��A���u�����Ȃ����ׂɂǂ�����ׂ����I�ȕ��@�_��Nj�����K�v������ł��傤�B�����O�̃T�E���h���\���ɐ������X�L���A�b�v���]�܂�܂��B |
 |
| 1: ���֓��x���@��ʌ���\�@�z�J�s���告�͒��w�Z ���� �i�w��:�c���G�a�j���o�� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�̌��u�����t�v����i�q.���I���J���@�b���^�����O�a�j�N���A�ŏd���ȁA�S�n�悢�T�E���h�ŃX�^�[�g�����ۑ�ȁB6/8�̃}�[�`�̃��Y���W�J�����炵���A��������ƃA�i���[�[���{���ꂽ�G���ł����B�I�[�P�X�g���[�V�����I�ȃo�����X���▭�ŁA�Ȃ�Ƃ����Ă��A�ׂ������������A�g���I�ł̗��ł��̘A�����A�Ë��̂Ȃ����y�̐ςݏd�˂����W�����A���N�̃R���N�[����ʂ��Ă��ō���̉ۑ��2�Ԃ������Ǝv���܂��B���R�Ȃł��A���̗��f���̂悢�T�E���h�͌��݂ŁA���Ƀ��j�]���̐��x���k�����A���F�̔������A�n���Ɛc���[���ŁA�I�n���S���ĉ��y�ɐg���䂾�˂邱�Ƃ��o�����Ǝv���܂��B�g�D�b�e�B�������Ă��邳���Ȃ炸�A�L���ȃT�E���h��W�J���Ă��܂����B�S�̂�ʂ��āA�X�ɉ��y�̏�̂悤�Ȃ��̂��\�������ƁA���y�̎��������A�b�v���čs���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |
| 4: ���C�x���@���m����\�@���i�s�����i���w�Z ���� �i�w��:�����q�j3�x����5��� �ۑ��1: �ʼnʂĂ̏�̃[�r�A�i�����p��j ���R��:�������u���[�}�̕����v����iO.���X�s�[�M�^�����q�j���ɃG�b�W���������A�̗͂̂���T�E���h�ŃX�^�[�g�����ۑ�Ȃ́A���ʂɏ�����Ă��鎖���ߕs���Ȃ��\������D���ł����B�����A���܉��̏������G�ɂȂ����肷�镔��������A��莩�R�ŖL���ȉ��y�̗���⋿����Nj����ė~�����Ƃ���ł��B�܂��A�ׂ��������~�X���c�O�ł������A���y�̗v�f�̂ЂƂЂƂ���������Ɨ���グ���A�g�ݗ��Ă�ꂽ�A�i���[�[�̍s���͂������t�ł����B���R�Ȃ̓^�C�g�Őc�̒ʂ����T�E���h�Ɖ��y��肪�G��ł����B���̍����▭�ȃA���T���u�����S�n�悢����Ԃ����グ�Ă��܂����B����Ȓ��ŁA�g�D�b�e�B�̋������A�s�p�I�Ȃ��̂����łȂ��A���ӂ�̂����������~���������̂ƁA�g�����{�[���̃T�E���h�����o���h���痣�����Ă����̂��c�O�ł����B�������A�S�̂�ʂ��āA�n�[���j�[�������������킽��S�n�悢���y�̃V�����[����ꂢ���ς��ɍ~�蒍����Ă��������������Ǝv���܂��B |
| 9: ���֓��x���@��t����\�@���s�����䍪���w�Z ���� �i�w��:���˒��_�j3�x����10��� �ۑ��3:�u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j ���R��:�ʉ_�̗����`���t�y�̂��߂́`�i���������j�ۑ�Ȃ̖`���̃n�[���j�[�͂܂�Ő��n��̂悤�ȃg�[���ŁA���̌�̖؊ǂ̃��j�]���́A��l�̑t�҂������Ă��邩�̂悤���k�����B���̎��_�őS�Ď����čs���ꂽ�����ڂ̉ۑ�Ȃł����B�܂��Ɋ��������y�Œ������̑f���炵�������N���̊����鎖���o���܂����B����Ȓ��ŁA�Ŋy��Z�N�V�����ɂ����ăX�l�A�����ɗ�Âɉ��y�̑g�ݗ��Ăɏ]���č��܂�Ă���̂ɔ�ׂāA���̊y�����Ɍ��ՑŊy�킪�A���X���_�o�ɒ@����ʂ�����悤�Ɋ�����ꂽ�̂��ɂ��������Ǝv���܂��B���R�Ȃ́A���X�܂ŃA�i���[�[���{���ꂽ�����ŁA�����̃u�������������Ȃ��قǂ̏W���͂ƁA���j�]����A���T���u�����k�����ɒE�X�́A�������ɂƂ��Ă͂��̏���Ȃ��K����12���Ԃł����B�l�I�ɂ͂��̃T�E���h�Ɖ��t�͂ɂ��A�����W���̂Ȃ������Ă݂��������͂��܂����B |
| 12: ���x���@���{��\�@���s����A���w�Z ���� �i�w��:��R��j���o�� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�̌��u�g�D�[�����h�b�g�v����iG.�v�b�`�[�j�^�㓡�m�j��⑬�߂�6/8�ł������A���j�]����؊ǂ̃n�[���j�[���������������A�^�C�g�Őc�̒ʂ������y�ƃT�E���h�ł����B�����A���̑��߂̃e���|�̂������A�I�n�W�X�Ɖ��y���i�݂����������������̂��c�O�B���Ԃɒǂ��Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ł���A�œK�ȃe���|�̖͍��Ƃ����̂����߂���Ƃ���ł��B�I�Ղ̓A���T���u���ɂ������ȃu���������܂����B���R�Ȃ́A�悭�P�����ꂽ�A���T���u���ƁA�L�т̗ǂ��T�E���h���G��ł������A�S�̓I�ɉ��̏������e�G�ȕ���������ꂽ�͎̂c�O�ł��B�������A���̌o�����o�āA���㌀�I�ɃX�L���A�b�v���čs���̂ł��傤�B�������̉��t���A���w���Ƃ��Ă͍������x���̃X�L�������������t�ł����B |
| 14: ���x���@���Ɍ���\�@��ˎs�����R�܌��䒆�w�Z ���� �i�w��:�n�ӏG�V�j2�N�A��11��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�傢�Ȃ�̑�n�`�`���M�X�E�n�[���i��؉p�j�j�ȑO�܂ł́A�S�̓I�ɂ��������܂�̂���T�E���h�Ƃ����C���[�W�ł������A���N�̉��t�͂������V������A�N���A�ŏd�ʊ��̂���T�E���h�ɕϐg���Ă��܂����B6/8�̃e���|�ݒ�ƃ��Y�������f���炵���A�O�i���̂���}�[�`�Ɏd�オ���Ă����Ǝv���܂��B�A�i���[�[���悭�{����Ă��܂������A�n�[���j�[���X�ɃN���A�ɂȂ�ƁA�S�ɋ��_�ƂȂ鎖�ł��傤�B�X�ɁA�����ł̃e���|�̗���ƁA������A���T���u���̃u�������̎��ԑт̉��t�Ȃ�Ί�����ڎw�������Ƃ���ł��B���N�̒��w�̕��́A�}�C���h�X�P�[�v�ƃ`���M�X�n�[���Ղ�ł������A�g������͂�`���M�X�n�[���B���t���ꂽ�����y�Ȃ̒��ł��A�悭�A�i���[�[���{���ꂽ�A�y�Ȃ̐��E�ς�I�m�ɕ\�������D���������Ǝv���܂��B���j�]�����k���Ȃ����łȂ��A��������Ɛc�������Ă���̂��A���y�S�̂�傫���������Ă��܂����B�܂��e�B���p�j�̃T�E���h���NJy��Ƃ̌��ˍ����̒��ŁA�n������ň�̉����Ă����̂���ۓI�ł����B�W�X�Ƃ������y�̗���̒��ɂ��A��������Ǝ咣���������G���ŁA���w�̕�����߂������Ă��܂����B |
| 2: �k�C���x���@�D�y�n���\�@�D�y�s�����Β��w�Z ��� �i�w��:���Čb���q�j3�x����5��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:���t�y�̂��߂̕��i�u�z������Ƃ��v����i�������j�����W�̖L���ȃT�E���h�ŃX�^�[�g�����ۑ�Ȃł������A���6/8�̃}�[�`�ɏd���������܂����B�����Ƒΐ����Ƃ̃o�����X���ɂ���l�̗]�n����ł��B�I�Ղ͍X�Ȃ�A�i���[�[�ɂ�鉹�y�I�Ȑ������]�܂��ł��傤�B���R�Ȃ̓t�@���t�@�[������̃X�^�[�g�ł������A�n�[���j�[����������Ƃ����A���ʂɏ�����Ă����ȏ�̃A�v���[�`���]�܂��Ƃ���ł��B���̌�́A�ْ������������W���͂ŁA���X�g�܂ŋ삯�����čs���܂����B�X�̑t�҂̉��t�͂ɂ͍������̂������܂������A���ꂼ��̔������ׂ�����������A���R�ȃt���[�W���O���悤�Ɋ��������铙�A���y�����^�C�g�ɕ���������@�_���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |
| 3: �����x���@��������\�@�o�_�s����ꒆ�w�Z ��� �i�w��:�i�^��j�R�x����42��� �ۑ��3:�u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j ���R��:�������u���[�}�̍Ձv���A�\�N�ՁA�\���ՁA�匰���iO.���X�s�[�M�^�X�c��_�j���ɃV���t�H�j�b�N�ȋ������������o���h�ł��B�ۑ�Ȃɂ����镈�ʂ̍Č��͔͂��Q�ŁA���̍����A���T���u���A�����̕��������������Ă��܂����B�a�̐����̉̂��������Ɏ��R�Ȃ��̂������܂����B�����A�S�̂̃T�E���h�̃o�����X��A�e���|�ݒ�ȂǁA��l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������l�߂���Ȃ��܂܂ɑS�������}���Ă��܂��������������ł��傤���B���R�Ȃ͎�t�����ɂ�����n�[���j�[�̏d�˕��̕s���R�����܂������܂����B���y�I�ȃ����n�����܂��܂�������ł��t������]�n�͂������͂��ł��B�������A�X�̑t�҂̃��x���͔��ɍ������̂�����A��Âȉ��y�^�т͒��w���̈���Ă��镔�����������܂����B���݂̎w���҂͕��C��N�ڂł����A�b�܂ꂽ�f�ނ������ɒ����点�邱�Ƃ��o����̂��A����̎�r�Ɋ��҂������Ǝv���܂��B |
| 5: ��B�x���@��������\�@�����s�����u���w�Z ��� �i�w��:�e�n����j���o�� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:���b�L�[�h���S���`��ܕ����ۂ̋L���i�����O�a�j�_�C�i�~�b�N�ŃN���A�ȃT�E���h����X�^�[�g�����ۑ�Ȃł����A�������X�g���[�g��������������A������ꂽ�T�E���h��肪�]�܂�܂��B�}�[�`���͖̂�����������A����̂������݂��S�n�悢���E�ς�����Ă��܂����B�����A���X�A�i���[�[�s���̊��͔ۂ߂��A���y�I�ɍׂ����������{���Ăق��������Ƃ���ł��B���R�Ȃ́A�S�̂�ʂ��ăA���T���u���̐��x�����炵���A�y�Ȃ̎����E�ς�I�m�ɕ\�������D���ł����B�������A�^���M���O�����ɂ��ꂢ�ȃT�E���h�Ƃ�����ۂ̂��鉉�t�͂�������ŁA���y����ʏ�ʂŃu�c��čs���̂��c�O�ł����B���y�������ɗ���������Ėa���ł������A���̕ӂ�͏܂̐F�𐱂ݕ����鋫�E���̂ЂƂł��B |
| 7: ��B�x���@��������\�@�����s�����ő�O���w�Z ��� �i�w��:��茛��j���o�� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�傢�Ȃ�̒n�`�`���M�X�E�n�[���i��؉p�j�j���C�����Ƃ����ۑ�Ȃ̃X�^�[�g�ł������A�S�̓I�ɉ��̏������e�G�ŁA�I�n�S�Ă̊y�Ȃ̃p�[�c���荇���Ă��銴���ŁA���ׂ��ȉ��y�I�������{���Ăق��������Ƃ���ł��B�����Ƒΐ����̃o�����X�������܂ЂƂŁA�����炭�e���|�̑������S�Ẳ��y�I�ȏ�����e�����Ă��܂����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���R�Ȃ͉������N���A�Ɍ�����A�X�̉��t�͂̍����̂킩��D���ł������A�g�D�b�e�B�ł͂�≹�̑��肪�������A���y�̑g�ݗ��Ď��̂ɂ��X�Ȃ�A�i���[�[�̗]�n���������悤�ł��B�܂��Ŋy��͒@���ăA�N�Z���g��t����̂��ړI�ł͂Ȃ��A���y�ɍʂ��Y�����i���Ƃ������@�_�ŗՂ�ł݂Ă͂������ł��傤���B |
| 8: �����x���@�R������\�@�h�{�s���K�R���w�Z ��� �i�w��:�������i�j3�N�A��10��� �ۑ��3:�u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j ���R��:��т̓��iC.�h�r���b�V�[�^�^���r�v�j�l�������Ȃ��Ȃ���A�ʂ�̗ǂ��n�[���j�[�ŃX�^�[�g�����ۑ�Ȃł������A�S�̓I�Ƀs�b�`�����s����ŁA���j�]���ɂ��u���������܂����B�������A�����̉̂������͎��R�ŁA����̂����a�̐��E�ς����܂��\�����Ă����Ǝv���܂��B�����A�NJy��̉��ʂɑ��āA�Ŋy�킪��⋭�߂������ł��傤���B���̕ӂ�̃o�����X�͐l�������Ȃ��Ȃ�Ȃ�قǁA����Ȃ��ė���̂ł��傤�B���R�Ȃ́A���̐l���̏��Ȃ����t��Ɏ�����I�ȂŁA�n�[���j�[���������A�������N���A�ȍD���ł����B�h�r���b�V�[�̐��E�ς��悭�\�����Ă��܂������A��≹�y�����R���������ȂƂ�����ۂł��B�������A�l�������Ȃ��Ȃ�ƌX�̑t�҂̉��t�͂������킯�ł����A���̕ӂ�͔��Ɉ��S���ĉ��y�ɐg���ς˂鎖���o���܂����B |
| 10: �����x���@�����s��\�@�ʐ�w�����w�� ��� �i�w��:�y���a�F�j2�N�Ԃ�12��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�J���g�D�X�E�\�i�[���i��؉p�j�j���ɃN���A�ȃT�E���h�ɂ��S�n�悢�}�[�`�̃X�^�[�g�ł����B6/8�̃��Y�������܂��Č�����A�����n������������D���������Ǝv���܂��B�X�Ƀ��j�]���̐��x�������ƁA�����������яオ�鎿�̍������y�ɓ��B�ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A�NJy��̃o�����X��Ŋy��Ƃ̃o�����X�Ȃǂ͐▭�ŁA�����s����̐����̑f���炵���������܂����B���R�Ȃ́A��t�̃n�[���j�[���������A�R���g���X�g���n�b�L�������D���ł������A�㔼��⑧�ꂵ���̂��A�T�E���h�̗̑͂��s�����ĕ������ė��܂����B���ԕ����X�Ȃ�F�t�����~���������Ƃ���ł��B�������A�\���y��̋���������ŁA��������Ƃ����咣�����������E�ς��Č����Ă����Ǝv���܂��B |
| 13: �k���x���@���䌧��\�@���s���O�����w�Z ��� �i�w��:����W�j���o�� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:���C�E�u�[�W�F���[�̎^�̂ɂ��ϑt���iC.T.�X�~�X�j�ۑ�Ȃ͓K�x�ɑO�i�͂��������A�e���|�ݒ���▭�ȍD���ł����B�k���̃o���h�炵���A�g�����y�b�g�𒆐S�Ƃ������NJy��̋������������A�ǑŊy��S�̂̃o�����X����������ƂƂ�Ă����Ǝv���܂��B����Ȓ��ŁA���X�ł��A���T���u���┭���Ƀu��������ꂽ�̂��c�O�ł����B�������A���邭�ăN���A�ȑO�����̃T�E���h�͐S�n�悭�����Ă��܂����B���R�Ȃ͋Z�p�I�ȓ�Ȃɒ���ł��܂����B���A��͂蒆�w���̗̑͂ł́A���ɑ����ׂ��ȃt���[�Y�̓A�b�v�A�b�v�ŁA���ꂪ�����̃~�X��u���Ɍq�����Ă��܂��܂����B�������A�R���[���̔��������A�L�����ƌ��镔�����������������o���h�ŁA���������`�������W���_�����킸�A���t���鑤�����������y���߂鉹�y�̒Nj�������������čs���Ăق����Ǝv���܂��B |
| 6: �l���x���@���쌧��\�@�����s���������w�Z ���� �i�w��:���q�i�j���o�� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�傢�Ȃ�̒n�`�`���M�X�E�n�[���i��؉p�j�j�N���A�ł܂Ƃ܂�̂���T�E���h�������Ă���o���h�ł����A�S�̓I�ɉ��F���X�g���[�g�Ń��A�Ȋ������܂����B�X�̃p�[�g�ɂ����čł���������������ɒNj����čs�����Ƃ�����Ǝv���܂��B�܂��A6/8�Ƃ��Ă͂��P���|�ݒ���������������ŁA���킵�Ȃ��}�[�`�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�ׂ����t���[�Y�������ꂪ���ł������A�����̉̂����͎��R�ōD�������Ă܂����B���R�Ȃł́A���̐��E�ς��悭�����������t�ɂȂ��Ă��܂������A���A�i���[�[�s���̊��͔ۂ߂��A�����������œ_�{�P�ɂȂ��Ă��܂��܂����B����Ȓ��ŁA�����̉̂�����A�n�[���j�[�̍����͎��R�ŁA�S�n�悢��������o���Ă��܂����B |
| 11: ���k�x���@��茧��\�@�����s���k�˒��w�Z ���� �i�w��:�g�c�N�j���o�� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�X�y�C����z�Ȃ���iN.�����X�L�[���R���T�R�t�^�����O�j�ۑ�Ȃ̖`���́A���ɃX�g���[�g�Ń��A�ȃT�E���h�Ƃ�����ۂŁA�S�̂̃o�����X���A�ቹ�y�킪��⋭�߂��ȂƂ�����ۂł����B�}�[�`�̗��ł����s�b�`�����s����ŁA�S�̓I�ɑO�i�͂����������y�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������A�g�����y�b�g���A�����y��̋����͔������L�т₩�ŁA���̃T�E���h�𒆐S�ɁA���ꂼ��̊y��̃T�E���h�������������̂Ɏd�グ�čs����������̉ۑ�ł͂Ȃ��ł��傤���B�t�҂̉��t�͍͂����̂ŁA���������������T�E���h��肪�]�܂�܂��B���R�Ȃ́A�R�����ɑ����ē��k������������I�Ȃ��͂��܂����B�S�̓I�ɗ��V�ȉ��y�������Ă���Ƃ�����ۂł������A�A���T���u�������G�ŁA�ׂ����t���[�Y�����������Ă����̂��c�O�ł����B�������ASAX�Z���N�V�����ɂ��J�f���c�@��t���[�g�A�N���A�I�[�{�G�̃\�����A�L�����ƌ��镔�����������������A���オ�y���݂ȃo���h�ł��B���݂ɗv��Ȃ����ł����A���̊w�Z�Ƃ̓z�e�����ꏏ�ł����i�j�B |
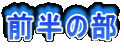 |
| 1: ���֓��x���@��t����\�@���s���������w�Z �����i�w��:�Γc�C��j3�N�A��25��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:���E�t�H�����E�h�D�E�V���N�E�A���[���E�V�����W���E�R���E���E�J���C�h�X�R�[�v�i�V�쐳���j�ۑ�Ȃ̖`�����璩��ԂƂ͎v���Ȃ��A������T�E���h�Ń}�[�`���X�^�[�g���܂����B�ׂ��������ł́A�T�E���h���X�g���[�g�߂����ۂ���������A�A���T���u���������Ɋ��ݍ���Ȃ�����������ꂽ��ł����A�S�̂�ʂ��āA�悭�A�i���[�[���{���ꂽ�A���̊y�Ȃ̊����^��掦���邱�Ƃ��o�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�g���I�O�̃V���o���̃N���V�F���h�͂����Ȃ���A���ȉ��o�ł��B���R�Ȃ́A�킵�̃n�[���j�[�ƃA���j���C�Ȑ����̗��݂��S�n�悭�A���̃o���h�̃T�E���h�̈��芴���⊶�Ȃ��������Ă��܂����B�\���y���僁����S������y��Ɋւ��ẮA���h��̉��₩�ȗh�炬���~���������Ƃ���ł����A�����͍��Z���炵������^�������̂��A���̊y�Ȃɂ����銮���x�Ƃ��Ă̕�����Ȃ��������ł��傤���B�܂��A���ۍ��Z���ł����E�E�E�E�B�ނ炪��l�ɂȂ��Ă܂��������̋Ȃ����̃����o�[�ō��t���鎞����������A���̂Ƃ��̔N��Ȃ�ł͂̉��̉��h������������A���̃^�C�g���̈Ӗ��ɂ��Ă��A��荇�������o����̂����m��܂���B����ɂ��Ă�������̃g�b�v�o�b�^�[����A���Ƀ^�C�g�Ŏ咣���������T�E���h�Ɖ��y�����\�����Ē����܂����B |
| 7: ���C�x���@���m����\�@���m�H�Ƒ�w���d�����w�Z �����i�w��:�ɓ��G���j2�N�A��37��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�����i�ۉȗm�j�ۑ�Ȃ̃C���g���͂��e�G���ȂƎv������̂ł������A�ǂ���炱��͓��C�n��̃}�[�`�݂̍���̓����̂悤�ł��ˁB���̌�̖؊ǂ̃��j�]���͌����Ɉ�̉����Đc�̂���T�E���h�ƂȂ�A���ɃX���[�X�ȗ�����������}�[�`�Ɏd�オ���Ă��܂����B�S�̂�ʂ��āA�������ۗ����A��ʂ��Ƃ̃T�E���h�̕ω����������B��≹�y�≹�F���c�����ȂƊ����镔���������܂������A�قǗǂ��A�i���[�[���ꂽ�D���������Ǝv���܂��B���R�Ȃ̖`���́A��ppp����X�^�[�g���܂������ABD�̃��[�����`���S�����������A����͂�����Ƃ�肷�����ȂƂ�����ۂł����B����Ȓ��ŁA�N���̃��j�]���ْ͋��������܂��`�������̂ɐ������Ă����Ǝv���܂��B���̌�́A�����A���T���u�������G���ŁA�y�Ȃ̎����E�ς��[���ɒ掦���Ă��܂����B�g�D�b�e�B�̃T�E���h�����ł����邩�ȂƂ�����ۂł������A�I�Ղ͐����̕��������������������ŁA�����ւ̓����͌����Ɋ����������Ă����悤�ł��B |
| 8: �k�C���x���@�D�y�n���\�@���C��w�t����l�����w�Z �����i�w��:��c�d�F�j3�N�A��32��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:���t�y�̂��߂̕��i���u�z������Ƃ��v���i�������j�قǂ悭�u�����h���ꂽ�T�E���h���S�n�悢�C���g������X�^�[�g����6/8�̃}�[�`�́A���e���|�ݒ肪���߂ł������A�T�E���h�����y���}�[�`�����x�Ȉ��芴���������G���ł����B���j�]���̓��ꊴ�A�n�[���j�[�̃u���̖�����A�����Ƒΐ����̗��݂����݂��ɂ߂�w�͂̐Ղ����肠��ŁA�R�����g���͂��ޗ]�n�̖������y�����グ�Ă��܂����B�����A���ɃT�E���h�ɒ@������悤�ȕ����������ꂽ�̂������A�c�O�������ł��傤���B���R�Ȃł̓t���[�g�̃\�������y�̐��E�ς���]������̂ɐ������A���̌�̃g�D�b�e�B�ɋÏk���ꂽ�t�҂����̐��܂����p���[�Ǝv���Ɉ��|����܂����B�A���T���u���̊m�����͖ܘ_�A������ׂ����t���[�Y�̂ЂƂЂƂ��ߕs���Ȃ��a���ōs�������y�i�s�͂ɂ͒E�X�ł��B��J���A�������킸�Ƀq�����Ƃ�����ꂽ����������܂������A���t���I����Ă݂��炻��Ȃ��Ƃ���鎖���̂����Ӗ��Ȃقǂ́A�������a�����Ă��܂����B |
| 12: ��B�x���@�F�{����\�@�ʖ����q�����w�Z ���� �i�w��:�ēc�^��j3�x����6��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�X�̑��蕨�i����i�j�L���ȃT�E���h�ɂ��ۑ�Ȃ̃C���g���ł������A��≹�����ł��A���ȃn�[���j�[�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�؊ǂ̃��j�]���͔������T�E���h�����o���Ă��܂������A��₻�̐��x�͊Â������ł��傤���B�܂��炵����ʔ����~�X���U�����ꂽ��A�v���v���Ńe���|���u���邽�߂ɉ��y������Ă��܂��̂��C�ɂȂ�܂����B�S�̂̍��t�ł́A�N���A�ȃT�E���h�����グ�Ă��܂������A�X�Ƀg�D�b�e�B�̃T�E���h���X�b�L������ƁA�S�ɋ��_�ƂȂ鎖�ł��傤�B���R�Ȃ́A�▭�Ȏ��芴���������؊ǃT�E���h�������I�ȂŁA�y�Ȃ̐��E�ς�I�m�ɉ��o���Ă��܂��B�����ɓo�ꂷ��g�����y�b�g�́A�������t�͂������Ă��܂����A���؊njQ�ɖ�����Ă��܂������ŁA�X�ɓ˂�������悤�ȃG�b�W�Ɖ��ƋP���������A���̃T�E���h�̐S�n�悳������I�ɃA�b�v����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�S�̂�ʂ��āA�����S�^�]�ȃe���|�ݒ�ł������A���y�ŐX�ї��o����̂ł͂Ȃ����Ǝv���قǂ̉���Ԃ̑g�ݗ��Ă͂������ł����B |
| 2: �����x���@���R����\�@ ���R�w�|�ٍ����w�Z ����i�w��:����d���j3�x����12��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�F���̉��y�iP.�X�p�[�N�j�������N�����̃o���h�̃T�E���h���Ă��܂����A����͂��̏o�����̂����������Ă��A�S�̓I�ɉ��̂Ȃ��A���@���ȃT�E���h�ɂȂ��Ă����̂��c�O�ł����B�ۑ�Ȃ̓T�E���h�̃o�����X�������A�u�����h�������܂ЂƂŁA���y�̃x�N�g�����B���ɂȂ��Ă�����ۂŁA��ʓ]�����X���[�Y�ɂ������A���y���א�ɂȂ��Ă��܂����B�ܘ_�A�X�̑t�҂̍������x���ł̉��t�Z�ʂ��N���A������ł̘b�ł����E�E�E�E�B���R�Ȃ́A�Z���ۑ�Ȃ�I�ɂ�������炸�A�`������z�����̃\�������킵�Ȃ��A�r�b�O�o���ւ̓��������B���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂����悤�ł��B�S�̂�ʂ��ăO���[�h�̍����y�Ȃ����Ȃ����t���Ă���킯�ł����A���낢��Ȃ��̂��l�ߍ��݂����āA�œ_���ڂ₯�Ă��܂�����ۂł��B�������A���Ղ̃A�O���b�V�u�ȃu���X�̉�]���A�n�����j�A�̍����ȃR���[���ƃt�@���t�@�[���A�I�Ղ̐����ȃA���T���u�����X�A������x�������ň�������ԑтɎ��Ԑ����Ȃ������Ă݂������t�������̂͊m���ł��B |
| 3: ���֓��x���@��t����\�@�K�u��s���K�u�썂���w�Z ����i�w��:�ΒÒJ���@�j3�N�A��28��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�o���G���y�u����̐X�̔����v����iP.I.�`���C�R�t�X�L�[�^�ΒÒJ���@�j���`�w�|�ف`�����ďK�u��ƁA�T�E���h���������܂�₩�ɂȂ��čs���ʔ��������\���܂����B�C���g������}�C���h�ŐS�n�悢�T�E���h�ŃX�^�[�g�����}�[�`�A�܂�₩�Ȃ�����u�₩�ł�������������ۂł������A���̒��Ńz�����̍U���I�ȍU�ߕ�������a�������������Ă��܂����B�T�E���h�̃o�����X�������Ă��܂��������ł��B�g���I�ł͒������A�A���T���u�����s����ŁA�}�[�`�Ƀu��������ꂽ�͎̂c�O�ł��B�I�Ղ������̂��̃o���h�炵����ʁA�G�R�Ƃ������̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B���R�Ȃ́A�X�ɃV���t�H�j�b�N�ȃx�N�g�����T�E���h�ɉ����܂������A�������͂܂�₩�Ȓ��ɂ��A�X�ɃG�b�W���~�������������ŁA�ׂ����t���[�Y���s���ĂɂȂ��Ă��܂��܂����B�I�[�{�G�̃\���́A�ʒu�I�Ƀ{�����[�����������A�ܑ̂Ȃ������ł����B�S�̂�ʂ��ẮA�����W�̍L���V���t�H�j�b�N�ȃT�E���h�ƁA�؊njQ�̃A���T���u���̗��킳�������Ă��܂������A����͂��l�߂̑���Ȃ��������܂����B |
| 4: ���֓��x���@��ʌ���\�@�t�������h�����w�Z ����i�w��:�s��鑾�Y�j3�N�A��10��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�A�b�t�F���[�`�F�i�������j��]���āA�����O�̔��ɃN���A�ŏd���ȃT�E���h�����������̂͏t�������h���Z�B�T�E���h�����łȂ��A���y�̃x�N�g�������������������Ă��邩�炩�A���Ƀ^�C�g�ȋ����ɂ܂��͈��|����܂����B�A�i���[�[����������ƂȂ���Ă����ۂŁA���y�Ɏ����͂�����̂��A���̃o���h�̖a�������T�E���h�̓����ł��傤�B�X�ɃT�E���h�̐F�����̕ω������G�ɗ��ݍ����ė���ƁA�����������y�Ȃ̐^�����ɒB����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ۑ�Ȃ́A�u���̖����I�[�{�G�̃\������X�^�[�g�B���̃o���h�̖؊ǃZ�N�V�����̔������T�E���h���悭���������A���T���u���ɖ�������܂����B���̌�̒ቹ�y��Q�ɂ�鑬���p�b�Z�[�W�̃��j�]���́A�I�[�P�X�g���[�V�����������Ă��A���s���ĂɂȂ��Ă��܂��Ă����͎̂c�O�B���̌�����܃o���h�Ƒ��F�����A���邢�͂���ȏ�̍������t�͂�@���Ȃ��������Ă��܂������A�y�Ȃ����̃��x���Ɍ������Ă��Ȃ��������ȁA�Ƃ�����ۂ������܂����B���̃T�E���h���X�ɋP�����Ă����y�Ȃ̏o�����Ɋ��҂������Ƃ���ł��B |
| 5: ���C�x���@���m����\�@�����u���q�����w�Z ����i�w��:���쌪���Y�j4�N�A��13��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�̌��u��̋R�m�v�g���iR.�V���g���E�X�^���c��j���ɍd���ȃT�E���h�ŁA�j��͂̑傫�ȃC���g������X�^�[�g�������̂���}�[�`�ł����B�S�̂̃T�E���h�̃o�����X�A�Ŋy��̒@�����A���܌�����@������悤�ȃT�E���h�A���̃}�[�`��I�m�ɉ��t����ɂ͂��I�[�o�[�A�N�V�����A�I�[�o�[�E�t���E���ȁA�Ƃ�����ۂł����B���R�Ȗ`���́A�E�s�ȃz��������X�^�[�g���܂����A�s�b�`�����h�炬�C���������ł��傤���B���̌���������t�͂ŁA�V���g���E�X�̐��E�ς�H���Ă����܂������A�S�̂�ʂ��ăT�E���h���o�����C���������͎̂c�O�B���ʂ��ӎ�����̂ł͂Ȃ��A�����O�̃T�E���h�����F���X�ɖ����čs�������ɗ��K�̃x�N�g�������������A�K�����Ƃ��̉��y���������ϖe����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��� |
| 11: �����x���@�����s��\�@���C��w�t�����֑䍂���w�Z ����i�w��:���c�M���j3�x����9��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�o���G���y�u�����̌v��4�����A�ԑt�ȁE��i�E�I���iP.�`���C�R�t�X�L�[�^���c�M���j�����O�̃S�[�W���X�ȃC���g������X�^�[�g�����ۑ�Ȃ́A�؊ǂ̃��j�]���̐��x���f���炵���A�ЂƂЂƂ̗v�f��Ƃ�����ΉB�ꂪ���ȃn�[���j�[�������Ă�������ƍČ�����Ƃ����A���x�ȃA�i���[�[���{����Ă��܂����B�g���I�Ŏ�A���T���u���ɍׂ����u���������܂������A�S�̂�ʂ��āA�T�E���h�̃o�����X���f���炵���A�k���ɉ��y���g�ݗ��Ă�ꂽ�}�[�`�������Ǝv���܂��B���̃o���h�ׂ̈ɃA�����W���ꂽ���R�Ȃ́A�؊ǂ̃A���T���u������X�^�[�g�B�ׂ����p�b�Z�[�W����A���G�ȃt���[�Y�܂ł�������Ɩa����A�̂����܂ꂽ�ɏ�̐��E�ς����o���Ă��܂��B�����ł����j�]���̐��x�������A�\���y������肵�A�Ō�܂ŏW���͂��r��鎖�̂Ȃ��A�����������Ǝv���܂��B�N���V�b�N�̖��Ȃ��A���t�y�Ȃ�ł͂̃x�N�g���ŃA�����W���������x�̍������y�ł����B |
| 13: �����x���@�R������\�@�R�������h�{�������w�Z ����i�w��:���T��Y�j2�N�A��3��� �ۑ��3:�u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j ���R��:�p�K�j�[�j�E���X�g�E�C���E�E�B���h�i�����~�j�c�̒ʂ����T�E���h����X�^�[�g�����ۑ�Ȃ́A���y��ǂ����Ƃɕω����čs���T�E���h�̕ϗe���f���炵���A�����������E�ς����y�Ȃɑ����������o�ł����B�������̌J��Ԃ��ł��A�▭�ɂ��̃o�����X��ω������ĉ��F��ς��čs����@�͂������ł��B�S�̂�ʂ��āA��������ƃA�i���[�[���{���ꂽ���̍������t�ł������A���ԕ��ɂ����āA���m���Șa�Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂����̂��ܑ̂Ȃ������ł��傤���B�I�Ղ́A�����O�̐��x�̍����A���T���u�����S�n�悢�A�G���ł����B���R�Ȃ͐��E�ς���]���āA�������؊ǂ̃A���T���u������X�^�[�g�B���̃o���h�͖؊Nj��Nj��ɃT�E���h�≉�t�͂̎��������A�u�����h���ꂽ���y���A���ʂɏ�����Ă���ȏ�̐S�n�悳�����������Ă����̂����͂ł��B2�N�O�ɒ������ŕ������u���[���X��i�����ɏ㎿�ȉ��y�Ɏd�グ�Ă��܂������A�l�I�ɂ͂���������i�̕����o���h�̃T�E���h�ɉ�̂ł͂Ȃ����ȁA�Ǝv���܂����B |
| 15: ���x���@���{��\�@���ˈ������w�Z ����i�w��:�~�c���i�j2�N�A��7��� �ۑ��3:�u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j ���R��:�̌��u�L�����f�B�[�h�v���A���ȁA�E�F�X�g�t�@���A�^�́A���Y�鍐�A���̒����Ă悤�iL.�o�[���X�^�C���^C.�O�����h�}���j�ۑ�Ȃ̖`���́A��N�ɔ�ׂăT�E���h�̃����W���������Ȃ��A�Ǝv���Ȃ��畷���܂����B�������A������o�ꊴ����������Ǝ������C���g���ŁA����ɑ�����ʂł��k���ȃA���T���u���ƁA���x�̍������j�]�����A�㎿�ȉ��y�����グ�Ă��܂����B����Ȓ��ŁA�Ŋy��̃o�����X����⋭�����銴��������A�NJy��̃T�E���h���Ԃ��Ă��܂���ʂ��U�����ꂽ�̂��c�O�ł��B�����Ƒΐ����̃o�����X�������ƍׂ������v�炤���o���ق��������Ƃ���ł��傤�B�������A�S�̂�ʂ��ẮA�E�s�ȋ������������D���������Ǝv���܂��B���R�Ȃł��A�����k���ȃA���T���u���͌��݂ł������A�����ł��A�Ŋy��Ƃ̃o�����X�������A�S�̂Ƃ��Ă��@������悤�ȃA�v���[�`�����܌���ꂽ�͎̂c�O�B�g�D�b�e�B�Ȃǂł��X�Ȃ�T�E���h�̐L�т��~���������Ƃ���ł��B�������A�n�[���j�[�Ȃǂُ͈�ȂقǂɃN���A�ŁA���̍������t�͂��������o���h�ł���̂͊ԈႢ����܂���B |
| 6: �l���x���@���Q����\�@���Q�����ɗ\�����w�Z ���� �i�w��:���J����F�j�R�x����21��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�����ȑ�5�� �d�n�Z�����A��5�y���iG.�}�[���[�^�c�������j�C���g���̓T�E���h�̃u�����h��������̂����X�b�L�����������Ă��܂��܂������A���̃��j�]���͔������A�}�[�`�̑O�i�͂���������ƕۂ����D���ł����B���ɁA���Y���Ɛ����̃m�����Y���镔��������܂������A�̐S������������S�n�悢�}�[�`�Ɏd�オ���Ă����Ǝv���܂��B����Ȓ��ł��������}�[�`�̏ꍇ�ɂ́A�P�A���X�~�X�͍ŏ����ɂƂǂ߂������̂ł��B���R�Ȃ́A���y�킪�K�{�Ƃ�������}�[���[��i�̐��t�y�łɁA�R���N�[���Œ��킵�ė��܂����B���������A���N�̃T�E���h�͒�����̃T�E���h�����s���C���Ȃ̂ƁA�{�������܂芴����ꂸ�A�y��Ɗy��̌��Ԃ����肷���邽�߂��A�y�Ȃ̎����E�ς�掦����܂łɂ͎���܂���ł����B���������y�Ȃ����t�����ł̃T�E���h���A�����Ĕz�u�̖����܂߂āA���ׂ����͂܂��܂��������̂��ȁA�Ƃ�����ۂł��B�������A�����������g�݂́A�l�I�ɂ͔��芅�тŁA������`�������W���čs���ė~�����H�����ȂƊ����܂����B |
| 9: �k���x���@���䌧��\�@���䌧���������ƍ����w�Z �����i�w��:�A�c�O�j2�N�A��2��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�E�C���h�A���T���u���̂��߂̃R���`�F���g�iS.�u���C�A���g�j�ۑ�Ȃ́A���y�߂̃T�E���h�ŃX�^�[�g���܂����B�S�̓I�ɃA�i���[�[�s���̊����͔ۂ߂��A�œ_���ڂ₯�����y�ɂȂ��Ă����͎̂c�O�B�n�[���j�[�̃o�����X�̎����A�Ɨ������t���[�Y�̓n�[���j�[�̈ꕔ�Ȃ̂������Ȃ̂��A���ʉ��I�v�f�Ƃ̗��݂͂ǂ�����̂����X�A�܂��܂��l�߂čs���v�f�͂���悤�Ȉ�ۂł����B�ۑ�Ȃ��I���ƁA�S���������オ���Ĕz�u�`�F���W���s�����̂ŁA���͂�╦���Ă��܂����B�R�A�Ȏ���̃W���Y���Č������悤�Ȋy�ȂƂł����������ł��傤���B���i����A�W���Y��t�@���N�Ɏ��g��ł���Ǝv����o���h�����ɁA���Y���ւ̃m���Ɉ�a���������A�f���炵��4�r�[�g�̐��E�ς����グ�Ă��܂����B�����A�R���N�[���Ƃ�����ł́A�y������ʔ��������łȂ��A���������y�Ȃ������ɃX�b�L���Ɛ������ĕ������邩�A�Ƃ����A�v���[�`���~���������悤�ȋC�����܂��B |
| 10: ��B�x���@��������\�@�����H�Ƒ�w�����铌�����w�Z �����i�w��:���c�M�F�j3�N�Ԃ�28��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�����i�ۉȗm�j�ۑ�Ȃ̃C���g���̓n�[���j�[������A�N���A���Ɍ����ẴX�^�[�g�ƂȂ�܂����B���̌���S�̓I�Ƀs�b�`���t���b�g�C���̊y�킪���邩�炩�A�����������肹���A���̃}�[�`�̎�����₩�������������������o���鎖�͏o���܂���ł����B�܂��A�y�Ȃ̂ЂƂЂƂ̗v�f���Ȃ�ƂȂ��e���|�ɍ��킹�Čq���ł��������ŁA�g���I�����̃t�@�S�b�g�ƃo���g���T�b�N�X�̃o�����X���A�ׂ��������ɂ��C�������ė~���������Ƃ���ł��B���R�Ȃ́A�`�������łْ̋��������o�ł��Ȃ������悤�ł����A�ۑ�Ȃɔ�ׂ�Ɖ������͈���������Ă��܂����B�L���ȉ��ʂƌX�̑t�҂̍����Z�p�͂��������o���h�ł����A���̗v�f���ő���Ɏg���āA�k���ɉ��y��ςݏグ�Ă������g�݂��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��͂������Ă���o���h�Ȃ̂ŁA���Ȃ�A�v���[�`�Ɋ��҂������Ǝv���܂��B |
| 14: ���k�x���@��������\�@�����������{�����w�Z ���� �i�w��:���{�t�i�j4�N�A��10��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�����ȑ�1�� �֒Z�����A��4�y���iD.�V���X�^�R�[���B�`�^���ؓo�Áj�ۑ�Ȃ͔��ɃX�g���[�g�ȃT�E���h�̃C���g���ł������A���A���T���u�����G�R�Ƃ��Ă��܂����悤�Ɋ����܂����B���̃��j�]�������܂ЂƂ��x���Â��A���y�̏œ_���ڂ₯�Ă��܂�����ۂł��B�}�[�`�̃e���|��Y���͂����̂ł����A�g���I�ɂȂ��Ă��T�E���h�̕ω����Ȃ��A�S�̂�ʂ��ĕ��R�ȉ��y�ɂȂ��Ă����̂��c�O�ł����B�����̉̂����ɂ��Ă��A�X�ɍ��Z���Ȃ�ł͂̃A�v���[�`���o�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���Ă��č����́A�S���I�ɏܑ_���̑I�Ȃ��ڗ����܂����A�܂�����͂���ň������ł͂Ȃ��Ƃ��āA�������̃o���h�͈ӗ~�I�ȑI�ȁA�ҋȂɃ`�������W����p���ɑf���炵���������܂��B����̎��R�Ȃ��A�A���T���u�����ǂ����Ƃ����j�]���̐��x���ǂ����Ƃ��A���낢�댾���n�߂�L���������킯�ł����A���t�y�ɂ�邱�������y�Ȃ̃A�����W�����^���Ă��ꂽ���̎p���Ɍh�ӂ�\�������A����ȋC���ŁA�y���������[���������Ē����܂����B�����Ă߂���߂鉹�y�ƃT�E���h�̐S�n�悢�V�����[�S�䂭�܂Ŋ��\�����Ē����܂����I |
 |
| 6: ��B�x���@��������\�@���؏��q�����w�Z ���� �i�w��:���d���v�j4�N�A��19��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�ؗ�Ȃ镑���iC.T.�X�~�X�j�ۑ�Ȃ̃C���g������A�œ_�̒�܂����^�C�g�ȃT�E���h�����̋�C���������߂Ă��܂����B���̃��j�]���͐�i�ŁA���̌�̋��ǂ̏d�ˋ�̐��ڂ܂Ŏ��Ɍv�Z����s�������}�[�`�Ɏd�オ���Ă��܂����B�g���I�ł̃T�E���h�̕ω����������B���ɐ��^�ŁA���₩�ȉ���Ԃ����A�u���ȃ}�[�`���A���̋�C�����v���X�̃x�N�g���ɓ������悤�ł����B���������A�`���̕��ŏ�肩��V���o�����K�V�����Ɠ|��鉹�����܂������A�S�����h���鎖�Ȃ��A�����Ӗ��ŒW�X�ƃ}�[�`������ł����W���͂��������ł��B���āA�O��̃��x���W�Ƃ��đI�Ȃ��ꂽ���R�ȁA�ؗ�Ȃ镑�ȁB�`������A�^�C�g�ɍׂ����p�b�Z�[�W������ł����o���h�̎��͂��A���ՂȂ���I����W�J���������O���ł����B���Ղ̃\���y������ꂼ��̖�������������Ɖʂ����Ă��܂������A�s�b�R���g�����y�b�g�̃\�������܂��������A����͑S�̂̃T�E���h�����̃x�N�g�������������܂����B���������A���Ԃ̃~�X��҉悤�ƒc�������t�ґS���́u�C�v�����������y��I�NJy��̃T�E���h���N���X�^���ɋP���悤�ȉȊw�����܂ŋN�����A���X�g�͈����̃O���[�����������A�I�[�f�B�G���X�̑劅�т𗁂тĂ��܂����B |
| 8: ���֓��x���@�_�ސ쌧��\�@���l�n�p���w�E�����w�Z ���� �i�w��:��������j3�N�Ԃ�7��� �ۑ��3:�u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j ���R��:���C�E�u�[�W�����[�̎]�̂ɂ��ϑt���iC.T.�X�~�X�j �ۑ�Ȃ̖`���́A�d���ŃN���A�ȃT�E���h�����̓o�ꊴ�����߂Ă��܂����B���̌�̐����́A�����ƃT�E���h�ɕω����~���������Ƃ���ł����A�C���E�e���|�ɂȂ��Ă���̐����̉̂����A�o�b�L���O�̈��芴�͂������ł����B�p�[�g�����n�[���j�[�̃R���{���[�V�����������ł��B�����ꂪ���Ȃ��̌�̐����Q����������ƍČ�����A���y�I�ɏ[�������ۑ�Ȃ������ƌ�����ł��傤�B�S�̂�ʂ��āA�C���Ă��Ȃ����U�@�̉��y���A�D���x�傾�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�a�̐����̉̂������悭�l�����Ă��܂����B�e���|�͎���߂����������m��܂���B���R�Ȃ͉ߋ��̑I�Ȃ̃C���[�W�@����A�X�~�X��i�ɒ���B�Ŋy��̃L���L���T�E���h�ƊNJy��̃u�����h���S�n�ǂ��A���̌�̃R���[���́A����̒��ɂ��邩�̂悤�ȐS�n�悳�������Ă��܂����B���Ոȍ~�́A���W�������̂��A�����~�X��o�����X�̈����������Ă��܂������A�u���N�����́v�Ƃ����u�O�v�̋����͂���������Ă����悤�ŁA���X�g�̃I���K���g�[�����͋����A�����������ڂ̃G���f�B���O�Ɉ��|����܂����B |
| 13: ���x���@���{��\�@���{������H�ȍ����w�Z ���� �i�w��:�ےJ���v�j4�N�A��35��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�o���G���y�u�_�t�j�X�ƃN���G�v��2�g�Ȃ��@�閾���A�S���̗x���iM.�����F���^���c�_��j���̂Ƃ���A�}�[�`���s���Ȉ�ۂ̂��������̃o���h�ł������A���N�̉ۑ�Ȃ́A����Ă��Ȃ��X���[�X�ȃC���g������A���R�Ȑ����̗���A�����Ď���̂����T�E���h���S�n�悢�}�[�`�Ɏd�グ�ė��܂����B�g���I�́A��┭���~�X���U�����ꂽ��A�T�E���h�����������肷�镔���������܂������A�����āA�O�i�͂��������A����̂���}�[�`�Ɏd�オ���Ă����Ǝv���܂��B���R�Ȃ͏\���Ԃ�1�Ȃ̍ĉ��ł��B�I�n�؊ǂ��ׂ����p�b�Z�[�W��]���Ƃ���Ȃ��Č����Ă����̂ɂ͒E�X�ŁA�n�[�v�̎g�������O��̃_�t�j�X�̎��ɔ�ׂ�ƁA�㎿�Ȃ��̂����������Ă��܂����B�����A�閾���̃N���C�}�b�N�X�ł́A�X�ɃT�E���h�ɉ����~���������Ƃ���ł��B�S���̗x��́A��⑧�ꊴ�������Ɍ����A�͋Ƃʼn����ʂ��čs�����Ƃ�������������ꂽ�̂��c�O�ŁA�Ŋy����S�̂̃o�����X������Ă��܂����B���������A�����ė������������ƈێ������D���������Ǝv���܂��B |
| 14: �����x���@�����s��\�@�����s���Бq�����w�Z ���� �i�w��:�n�ꐳ�p�j2�N�A��11��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:���̒��˔n�`���t�y�̂��߂��i���������j�S���{�̐V�����ŕБq�`�[���̖ʁX�������������܂������A�����Ő��������t���ꂽ�ۑ�Ȃ��������胊�T�[�`�A�A�i���[�[���ė����̂��A�����s���̎��ɔ�ׂ�ƁA���̐��x�̓A�b�v���A�V���ȃA�v���[�`���y�Ȃ��X�ɃN���A�ɁA���̓I�ɉ��o���鎖�ɐ������Ă��܂����B���̃o���h�͂Ȃ�ƌ����Ă��A�t�҂����̉��t�͂̃N�H���e�B�̍�������i�ł��B���̊y�Ȃɓ���ꂽ�ЂƂЂƂׂ̍����v�f��]���Ƃ���Ȃ������o���A�����x���̃A���T���u���Ŗ��t�������鉉�o�ɁA��������Ɖ����Ă���̂��f���炵���Ƃ���ł��B���R�Ȃ́A���N�̂��̃o���h�̈Ϗ���i�B�^�C�g���̎��̒��˔n�́u�w����Œ��˂�i�W�����v����j�n�v�܂肱�̃o���h�̎w���҂̎���\���Ă�������ł��B�y�ȂƂ��Ă͉Ȍ˂ƃn���\�������̂����悤�ȃC���[�W�ł��傤���B�����s���ŕ������Ƃ��́A�Ŋy��ƊNJy��̃o�����X�̈������C�ɂȂ�܂������A���É��ł͌����ɏC�����Ă��܂����B���̓K���\�͂��������I���N�̃R���N�[���̑�g�����A����т₩�ō����ȋɏ�̃T�E���h�Œ��߂������Ă���܂����B |
| 1: ���֓��x���@��ʌ���\�@��ʉh�����w�Z ��� �i�w��:���́j2�N�A��23��� �ۑ��1: �ʼnʂĂ̏�̃[�r�A�i�����p��j ���R��:�̌��u���X�v�l�v����i�f.�v�b�`�[�j�^���q�W�j��������ƃu�����h����A�����O�̐c�̂���T�E���h�ŃX�^�[�g�����ۑ�Ȃł������A�`����┭���~�X���U�����ꂽ�͎̂c�O�B�������A���̌�́A���肵���T�E���h�ƁA�k���ȃA���T���u�����S�n�悢���E�ς����o���Ă��܂����B�������A���̉ۑ�Ȃ̓o���h�̎����Ă���͂�����̂����X����Ȃł͂���Ȃ��A�Ƃ�����ۂ����߂Ď���������ł��B���R�Ȃ̓K�����ƃT�E���h��ւ��āA�G�b�W�̂���T�E���h�ŁA�ׂ����p�b�Z�[�W���A�������Ɏ���܂ŁA��������ƕ�������̂ɐ������Ă��܂����B�f���炵���Č��͂ł��B�\���y��̏W���͂������A�I�Ղ��o���h�S�̂̋C�����̕����̓u���邱�ƂȂ��A�v�b�`�[�j�̂߂���߂����y��a�������čs���A���̂����悤�ȉ����ł����B���������A�O���̕��������ł������A���N�̃I�P�}���R�����̕��X�́A�N���V�b�N���y�̃Z���N�V�������̂ɑ��āA�ǂ���猵�����p���ŗՂ�ŗ����悤�ł��ˁB���Ɏc�O�Ȏ��ł��B |
| 2: �k�C���x���@�D�y�n���\�@�D�y���{��w�����w�Z ��� �i�w��:�ؓc�b��j3�N�A��3��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:���N�C�G������iG.���F���f�B�^���c�m��j�ۑ�Ȃ́A���G�R�Ƃ����T�E���h�Ɖ��y�ŃX�^�[�g���܂����B�S�̂�ʂ��Ă������I�ȃT�E���h���������o���h�Ƃ�����ۂł��傤���B���������̉ۑ�Ȃɂ��Ă̓A�i���[�[�̗]�n���܂��܂��������悤�ŁA���y�̏œ_���B���ɂȂ��Ă����̂��c�O�B���j�]���̐��x���A�X�Ȃ��������҂������Ƃ���ł��B�����Ă��̃X�g���[�g�ł���т₩�A���S�[�W���X�ȃT�E���h�͎��R�ȂŖ{�̂����܂����B�`���̃��x�����̓G�b�W�̂��鉹�y���A�y�Ȃ̐��E�ς�I�m�ɕ\�����Ă����Ǝv���܂��B�����A�S�̂̃T�E���h�̃o�����X�����܂ЂƂŁA������������Ă��܂�����������ꂽ�͎̂c�O�ł��B�܂����̌�A���F�̕ω�������ꂸ�A�I�n�����F�ʊ��ʼn��y���i��ōs���Ă��܂�����������܂����B��t�����������芴�������������ŁA�a���̏d�˕��ɂ��X�ɓ˂����A�v���[�`���]�܂��Ƃ���ł��B |
| 3: ���x���@���{��\�@����w�@�����w�Z ��� �i�w��:����쏺���j3�x����11��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:���ɂ̔g���i�����~�j�������̗ǂ��T�E���h�ŃX�^�[�g�����ۑ�Ȃł������A����܂Ŏ����Ă����C���[�W�ɔ�ׂ�ƃT�E���h����₱����܂�Ƃ�����ۂɂȂ��Ă��܂����B���y�I�ɂ͑S�Ă̗v�f���N���A�ɍČ����A�▭�Ƀo�����X������Ă��܂������A�T�E���h�̃����W���������߂��A���y�S�̂ɃX�P�[�����������Ă��܂����悤�ł��B�㔼�͔��ɒW�X�Ɖ��y���i��ł��������ŁA�Ō�̎R��o�肫��Ȃ��܂I����Ă��܂�����ۂł����B���R�ȂɂȂ��Ă��A�T�E���h�����܂ЂƂ˂������Ȃ���ۂŁA�I�m�ɍČ�����鉹�y�Ƃ͗����ɁA�X�P�[�����̕�����Ȃ��͔ۂ߂܂���ł����B�S�̂�ʂ��ă\���y��̋Z�ʂ������A�y�Ȃ̐��E�ς��m���ɍČ����Ă��܂������A���܃����f�B�̑t�ŕ��ɍ�דI�ȕ���������ꂽ�̂��l�I�ɂ͋C�ɂȂ�܂����B�������A�X�̑t�҂̉��t�͍͂����A�I�n���S���ĉ��y�ɐg���ς˂邱�Ƃ��o�����Ǝv���܂��B |
| 4: ���֓��x���@��ʌ���\�@��ʌ����ɓފw�����������w�Z ��� �i�w��:�F���m���j4�N�A��16��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�����I���Ȃ��@��P�E�R�y���i�r.���t�}�j�m�t�^�X�c��_�j���ɉ��ƕ\������T�E���h�ŃX�^�[�g�����ۑ�Ȃ́A�S�̂̃T�E���h���܂�₩�Ȃ�����A�������ۗ������A����̂����}�[�`�ł����B���y�̗�������R�ŁA�܂��ɉ����̐��֓��T�E���h�ɓރT�E���h�̌��݂Ԃ�������Ă��܂����B���R�Ȃ̌����I���Ȃ͑�3�y�͂̂݉��t����鎖�������̂ł����A���̃o���h�͑�1�y�͂���̃X�^�[�g�B�������܂���Ȃ��Ƃ������́A�R���N�[���ŕ���������̂�����Ƃ������ł�����܂��ˁB�����ɉʊ��ɒ���ł���̂��A���֓��o���h�̌����Ƃ��������ł��傤���B�������A��1�y�͓͂����t���[�Y�̉��V�I�ȓW�J�̊y�ȂŁA���y�̗��ꂪ�疟�ɂȂ��Ă��܂��̂͒v�����Ȃ��킯�ł����A�R���N�[���Ƃ�����ł́A��͂�L���ɓ������͖����̂ł��傤�B�����č������t�͂����Ă��܂������A��3�y�͂ʼn��y�I�ȗ�������I�ɕω�������ɂ͎���Ȃ������悤�ł��B�����čł��c�O�������̂́A���y�̗]�C��ł������Ă��܂����t���C���O����ł����B |
| 7: ���k�x���@��������\�@�������������ƍ����w�Z ��� �i�w��:���ѓ�O�v�j2�N�A��4��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�����ȁu��ƃ}�e�B�X�v����iP.�q���f�~�b�g�^�����j���̌ゾ����Ȃ̂��A���ɂ܂�₩�ł�₱����܂�Ƃ����T�E���h�����ɔ�э���ł�����ۂł����B�S�̂�ʂ��āA�Ŋy�킪���傫��������ۂ������ł��傤���B�NJy��̃o�����X�͗ǂ��A�������ۗ����A�n�[���j�[�����肵���D�������������ɁA�S�̂̃T�E���h�̃o�����X������܂�܂��B�g���I�ȍ~�́A�}�[�`�Ƃ��Ă̑O�i�͂͂�����̂́A���y���W�X�ƒP���ɂȂ��Ă��܂����̂��c�O�ł����B���R�Ȃ́A��͂蕟���̃o���h�炵���A���j�[�N�ȑI�Ȃ������Ă��܂����B�T�E���h�����y�����ɃV���t�H�j�b�N�ȃA�v���[�`�����Ă���o���h�Ƃ����C���[�W�ł��B�����ĉ������X�̑t�҂̉��t�͂̍������A���������I�Ȃ̃A�v���[�`����������Ǝx���Ă��銴���ŁA�k���ȃA���T���u����A�L�ȋ������������n�[���j�[�����ɐS�n�悢12���Ԃł����B |
| 9: ���C�x���@���m����\�@����w�������w�Z ��� �i�w��:�O�Y���i�j4�N�Ԃ�13��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�y���u�T�����v���A���̃��F�[���̗x���iR.�V���g���E�X�^���V�r�N�j���N���A���Ɍ�����C���g���ŃX�^�[�g�����}�[�`�ł������A���Y���̃L�[�v�����S�n�悭�A�O�i�͂̂���}�[�`�����o���Ă��܂����B�X�ɐ��������₩�ɍۗ����ē͂��Ă���ƁA���y���X�ɖ��邳�𑝂������Ă��傤�B����Ȓ��Ő����ŃA���T���u���̃u��������ꂽ�͎̂c�O�ł����B���R�Ȃ͐����ƃh���C�u���̂��铱�����ŃX�^�[�g���܂������A�I�[�{�G�\���̗���ȋ����ɑ��āA�o�b�L���O�����A�b�v�A�b�v�Ȋ����ŁA�d�����̌㉟�����o���Ȃ������悤�Ɍ���ꂽ�̂��c�O�ł����B�\��ɂ������Ƃ����ƕω����~���������Ƃ���ł��B����Ȓ��Ńn�[���j�[�̈��芴�͑f���炵���A�t�҂̉��t�͂̍��������������܂����B�I�ՁA���Ŋy�킪�o�����X������Ă��܂��܂������A����ȉ��y�̗���̒��ł���ÂɃR���g���[�����čs���A�v���[�`�����߂���Ƃ���ł��B |
| 10: ���k�x���@��������\�@���������֏鍂���w�Z ��� �i�w��:���{���l�j2�N�A��15��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�f�B�I�j�\�X�̍Ղ��iF.�V���~�b�g�^���{���l�j�ӊO�ɂ����J�ɉ����ނ��o�������̂���C���g������ۑ�Ȃ̓X�^�[�g���܂����B�؊ǂ̃��j�]���̔�������A�n�[���j�[�̈��芴�͌��݂ł������A�}�[�`�̃��Y�������Â��A���y�̗�������ɂ����~�߂Ă��܂�����ۂł����B�T�E���h����╽�������ȂƂ�����ۂĂ����傤���B�������A�g���I��̃A�i���[�[�͂͑f���炵���A�I�Ղ͔������Ƒu���������������G�b�W�̂��鉹�y�����グ�Ă��܂����B���R�Ȃ́A���炭���̃o���h�̏\���Ԃ̂ЂƂ́A���ҋȔŁB�o���h�S�̂̉��t�͂̍����ƁA�k���ȃA���T���u�����S�n�悢�G���ł������A�����t���[�Y�̃��j�]�����Ƀu�����U������A�T�E���h�≹�y���o�����Ă��܂�����ۂł����B�������A�y�ȑS�̂̐��E�ς̉��o�͂���̕��ŁA�I�Ղ̍��Z�x�����x�̃A���T���u���͈����ł����B |
| 5: �k���x���@�x�R����\�@�x�R�����������ƍ����w�Z ���� �i�w��:�_�c����j2�N�Ԃ�28��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�������u�h���E�t�@���v�iR.�V���g���E�X�^�勴�W��j�u���X�T�E���h�𒆐S�Ƃ�������т₩���������O�̖k���T�E���h�ł����A�ۑ�Ȃ̃C���g���́A�G�R�Ƃ��Ă��܂��A�����~�X������ꂽ���̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B���̌�̖؊ǂ̃��j�]�����l�߂��Â��A�S�̓I�ɏœ_���ڂ₯���}�[�`�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���̌�̃g�����y�b�g�̃A���T���u���̗��������͖k���o���h�Ȃ�ł͂̂��̂ł����A��͂�y��ƂȂ�T�E���h�A�A���T���u���̍\�z���挈�ł͂Ȃ��ł��傤���B�T�E���h�S�̂Ƃ��Ă��A���ɖ؊ǂ𒆐S�ɉ��̂��鋿����ڎw���Ă��炢�������̂ł��B���R�Ȃł��A���ǂ𒆐S�Ƃ������y�����{���Ă��܂������A�؊ǂƂ̃u�����h���Ȃ��ꂸ�A���߂ׂ̍����o�����X�̎{�������߂���Ƃ���ł��B |
| 11: �����x���@���R����\�@�A�������w�Z ���� �i�w��:���эI�j10�N�Ԃ�15��� �ۑ��1: �ʼnʂĂ̏�̃[�r�A�i�����p��j ���R��:�X�y�C�������Ȃ��@�Ղ��iM.�����F���^�X�c��_�j�`������A�T�E���h��n�[���j�[���������Ă���̂��C�ɂȂ�܂����B���F���̂���₱�����������ŁA�ׂ����p�b�Z�[�W���U���Ȉ�ۂɂȂ��Ă��܂��܂����B���̌�����y�����ʓI�ɐi��ł��������ŁA�������I�m�ɓ͂��Ă��Ȃ������̂��c�O�ł����B����Ȓ��ł��A�n�[���j�[�͈��芴�������o���A���Y���̍��݂����y�S�̂�S�n�悢���̂ɂ��Ă��܂����B���R�Ȃ́A�������ł͓��ȑΌ��𐧂��ė����X�y�C�������ȁB�T�E���h���悤�₭���ɂ�����ė��������ŁA�d�������������G�b�W�̂���T�E���h�����̃��F�[���E���ł����Ƃ�����ۂł����B�ׂ����t���[�Y���I�m�ɂ��Ȃ��A���y�������͎����Ă��������ł������A�X�ɋ��ǂƖ؊ǂ̃T�E���h�Ƀu�����h���������ƁA���y�̐F�ʊ��������̂ł͂Ȃ����ȁA�Ǝv���܂����B |
| 12: �l���x���@���m����\�@���m�������m�������w�Z �����i�w��:���R���V�j2�N�A��6��� �ۑ��1: �ʼnʂĂ̏�̃[�r�A�i�����p��j ���R��:�z�n���߂��i�����~�j�傫�߂̃g���̃T�E���h����X�^�[�g�����ۑ�Ȃ́A�������s���Ăȕ����������A�S�̓I�Ƀn�[���j�[�ɑ��肪������`�ɂȂ��Ă��܂����B�s�p�ӂȔ����~�X���U�����ꂽ�͎̂c�O�ł��B�X�̉��t�͎��͍̂������̂�����悤�Ɍ����܂������A��������ЂƂ̍�i�����グ�čs���Ƃ����A�v���[�`������x�������K�v������̂ł͂Ȃ����ȂƂ�����ۂł��B���R�ȂɂȂ��Ă��A�U���ȃT�E���h�ɕς��Ȃ��A�i���͂̌��������y�ɂȂ��Ă��܂����悤�ł����B�X�Ȃ�A�i���[�[�͂����߂���Ƃ���ł��傤�B����Ȓ��ł��T�E���h�̃N���A���͍D��ۂł����B |
| 3: �����x���@�����s��\�@���C��w���t�y������ ���� �i�w��:���{�M���Y�j4�N�A��7��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�։�̔����`�m�E�`�E��E�q�E���E�M�E�F�E��`�i�M���듿�j���N�́A�����̗\�I�`�{�I�A�����đS�����ƑS�Ẳ��t�����Ƃ��o���܂����B���̑S�Ă̏�ŁA���肵�������x�̍������t���c�����̂͗��ŁA�w���҂Ƃ̃R���r�l�[�V�����₨�݂��̐M���x�������Ƀ��x���A�b�v���ė��Ă���̂����������Ă��܂����B�d���Ȃ�����N���A�ȃT�E���h�͐S�n�ǂ��A�������N���A�Ȃ̂��t�҂����̒b���x�̍�����\���Ă��܂��B���̋������ӎ������z�u���������B�ۑ�Ȃ̏I�Ղ́A�o�X�g���̔j����≹�y�̕i�i���ז��������̂悤�Ɍ����܂������A����͂܂���u�̌��B���R�Ȃ͓����s�{�I�ɔ�ׂ�ƁA�a���ۂ̃o�����X�����ɉ��P���ꂽ�悤�ŁA�y�Ȃ̍��g�݂��V�[�X���[�ƂȂ銮���x�̍������t�ł����B�n�[���j�[�̈��芴�͖ܘ_�A�s���͂����A�i���[�[�ɂ������̍ۗ����������f���炵���A���t��͈������̊��т𗁂тĂ��܂����B |
| 10: ���֓��x���@�_�ސ쌧��\�@�_�ސ��w���t�y�� ���� �i�w��:���V�r�N�j2�N�A��42��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�o���G���y�u�����̕s�v�c�Ȗ�l�v���(B.�o���g�[�N�^���V�r�N)���l���ʼn��y��t�ł�Ƃ����s�ׂ��A���́A�l���ڎw���A������l�X���������o����̂��E�E�E�E�B���̃o���h�̉��t���Ȃ��炻��Ȃ��Ƃ��ӂƍl���܂����B�ЂƂ�ЂƂ�̑t�҂�����ƕς�炸����Ȃ���Âɂ��̃��[���i�����j�������A���̂ЂƂЂƂ̑f�ނ��}�G�X�g�����X�ɗ�Âɑg�ݗ��āA�C�������Ȃ�قǂɕ��G�Ȗ��t�����s���B�������ďo���オ�������y�̖��p�ɊϏO�������B����͂ЂƂ̊y�c�̗��z���ł���A����̐_�ސ��w�̉��t�́A�܂��ɂ��̗̈�ɑ��ݓ��ꂽ�悤�Ȗ��킢�������Ă��܂����B�悭�u�ڂ̊o�߂�悤�ȁE�E�E�E�v�Ƃ������t���g���܂����A����̉ۑ��5�Ԃ��āA�����Ȃ�̂��A�ڂ��o�߂�̂��E�E�E�E���̃o���h��5�Ԃ͂܂��Ɍ�҂ŁA�߂���߂���ʓ]���A�y�Ȃ̗v�f�ЂƂЂƂJ�ɖa���ōs���A�t�҂Ǝw���҂̉��y�̎��̍����ɒE�X�̎v���ł����B2���Ԃ�ʂ��āA�ł��A�i���[�[�̍s���͂����ɏ�̉��y�����������Ă��܂����B���R�Ȃɂ��Ăׂ͍���������˂��ΐF�X�o�Ă���킯�ł����A����ȍs�ׂ���邾�Ǝv����قǂɁA�ߕs���̖������y�̔Z�x��̊��o����12���Ԃ������Ǝv���܂��B |
| 1: ���x���@���{��\�@�ߋE��w���t�y�� ��� �i�w��:�X�����Y�j4�N�A��30��� �ۑ��1: �ʼnʂĂ̏�̃[�r�A�i�����p��j ���R��:�����ȑ�3�Ԃ��A��4�y��(J.�o�[���Y)���N�o��30��ڂƂȂ����ߋE��w�B�����Ԃ��ԁA���̃o���h�̉��t���Ă����킯�ł��B�̂���ς��Ȃ��A���X�d�h�ŏd���ȃT�E���h�͍��N�����݂ł����B���A�T�E���h�����y���S�̓I�ɂ�������Ƃ��������ŁA�ׂ����t���[�Y�ɂ��������ꂽ�͎̂c�O�B���������z�[���́A����ȍׂ�����������N���A�ɓ`����ė��Ă��܂��܂��B���ׂ̈��A�I�n��������������Ƃ����A�S�̓I�ɐ����̖͂������t�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���̃^�C�v�̃z�[���ւ̑s�\���������̂ł��傤���B���R�Ȃ́A���ǂ̔�������∫���A��������N���A���Ɍ����Ă����̂��c�O�B�܂������~�X���U������A����̗͂��ł��Ȃ��܂I����Ă��܂��������ł����B����Ȓ��ŁA��ÂɃ��Y��������ł����p�[�J�b�V�����̑��݂������Ă��܂����B |
| 2: ���֓��x���@��ʌ���\�@������w���t�y�� ��� �i�w��:���쐹��j3�N�A��22��� �ۑ��3: �u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j ���R��:�R���R���f�B�A�`���a�ɂ���ā`(�����~) ��A�o���h���������āA�N���A�ȃT�E���h�͐S�n�悩�����̂ł����A�炵����ʃA���T���u���̗��ꂪ��������ƁA��͂荡��̂悤�ȃz�[���Ƃ̑��������X���������悤�ł��B����ɂ��Ă��A�ۑ�Ȃ́A���ɑ����e���|�ݒ�B���t�͂̂���t�҂����͉����������e���|�ɕt���Ă����܂����A����̂悤�ȃz�[���̋����̒��ɂ����ẮA�I�n�������R���R�������y�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���R�Ȃ́A���̃o���h�̗킵���؊ǂ̉��F�Ƀ}�b�`���O�����I�Ȃł������A�ۑ�Ȃ̕s�����̂܂܂ɁA�`���������̂��c���ł��Ȃ��܂܂ɏI����Ă��܂����A�Ƃ�����ۂł����B����Ȓ��ł��A�S�̂̃T�E���h�̃o�����X��A�i���[�[�͂́A�������ŁA���̗͗ʂ�{�ԂŔ���������Ȃ������̂�����܂�܂��B |
| 4: ���x���@���s�{��\�@���J��w�w�F��w�p�����ǐ��t�y�� ��� �i�w��:��ы`�l�j3�x����18��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�����ȑ�5�ԁu�v���v���A��4�y���iD.�V���X�^�R�[���B�`�^��W�F�j�ۑ�Ȃ͎����O�̂܂�₩�ȃT�E���h�ŁA���J�ȉ��y���ɍD�������Ă܂����B�������ۗ����A�T�E���h�̃o�����X���▭�ȃ}�[�`�Ɏd�オ���Ă����Ǝv���܂��B���R�Ȃ́A������z���đ����̃o���h�����g��ł����A�����W���́B�`���́A�ۑ�Ȃɔ�ׂĂ��s�p�I�ȃT�E���h�����҂��Ă��܂������A�ۑ�Ȃ���̕ω��������Ȃ������͎̂c�O�B�A���T���u�������s���ȕ����������܂����B�܂����̋Ȃ�������ɂ́A�T�E���h����▾�邷���邩�ȁA�Ƃ�����ۂł����B�o���h�S�̂Ƃ��Ă��A�����ƒቹ���������Ă���ƁA���y�����肵�����ł��傤�B�������A���y�͔��Ƀ^�C�g�ȕ\���ŁA�؊ǂƋ��ǂ̃u�����h����S�n�悭�A�I����̓I�[�f�B�G���X����̊��т𗁂тĂ��܂����B |
| 8: ��B�x���@��������\�@�����H�Ƒ�w���t�y�c ��� �i�w��:�ēc�T��j3�x����14��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�������u���[�}�̍Ղ�v���A�匰���iO.���X�s�[�M�^�����r�Y�j�ۑ�Ȃ́A�c�̒ʂ����T�E���h���A���̌��݂Ԃ�������Ă��܂������A�n�C�g�[���ɂ��L�c�������������Ă����͎̂c�O�ł����B���y�I�ɂ͊G��I�ȕ\�������Ă���ȂƂ�����ۂł������A���̊y�Ȃɂ��Ă͂܂��܂��A�i���[�[�̗]�n���������̂ł͂Ȃ����ȂƎv����A��⒆�r���[�Ȏd�オ��ł����B���̌㏈���ɂ����J�����~���������Ƃ���ł��B���R�Ȃ́A�e���|�ݒ�̂������A�ׂ����t���[�Y���e�G�ɂȂ�A�����n���Ɍ������G�R�Ƃ������y�ɂȂ��Ă��܂����B�������A�u���X�Z�N�V�����̃X�g���[�g�ȃT�E���h�͑��ς�炸�̐S�n�悳�ŁA���̒���������͐���������Ȃ��������ȁA�Ƃ�����ۂł����B |
| 9: �k�C���x���@�D�y�n���\�@�D�y��w���t�y�c ��� �i�w��:����q���j2�N�A��11��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�R���[���O�t�ȁu�����A�l��A���̍߂̑傢�Ȃ��Q���v�ɂ�錶�z���i�ɓ��N�p�j�S�̂�ʂ��āA�T�E���h�����A�����邩�ȁA�Ƃ����̂��A�����Ȋ��z�ł����B���ꂼ��̊y��ŁA�p�[�g�ŁA�����đS�̂ŁA�����������F��Nj����ė~�������ȁA�Ƃ�����ۂł��B�ۑ�Ȃ́A�}�[�`�Ƃ��Ẵ��Y�����キ�A�ЂƂЂƂ̃t���[�Y���s���ĂɂȂ��Ă��܂��܂����B���R�Ȃł́A�N�����l�b�g�̃A���T���u���ɂ����āA�������ǂ��ۗ������邩�Ƃ����A�v���[�`���~���������Ƃ���ł��B�R���[���ɂ����Ă��A���y�����R�ɂȂ�Ȃ��悤�ȍH�v���~�������������ł��傤���B���Ɏ�t�����ł͂�肫�߂ׂ̍����A�v���[�`���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂��B��͂̂���o���h�Ȃ̂Ŏ��Ȃ�J�ԂɊ��҂������Ƃ���ł��B |
| 11: �����x���@�L������\�@�L����w���t�y�� ��� �i�w��:���i�c���j2�N�A��12��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:��㑭�w�ɂ�錶�z��(��I�T)�O������@����ɁA��w�̕��B��̊w���w���������Ǝv���܂��B�ۑ�Ȃł́A�w���҂Ƒt�҂���̂ƂȂ��������T�E���h�ɐS�n�悳�������܂����B���������A��͂�A�i���[�[�s���͔ۂ߂��A�����n���Ɍ������}�[�`�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�I�Ղ͉��y�I�ɂ��X�ɐ������K�v�������悤�ł��B���R�Ȃ́A���̃o���h�̎���̂����T�E���h���悭�}�b�`���Ă��܂������A�u�a�v�̃j���A���X���u�m�v�̊y��łǂ��\������̂��Ƃ����H�v�������Ɨ~����������ۂł��B�S�̓I�ɉ��y���܂�����Ƃ��Ă��܂��������ł��傤���B�I�ՂɌ���ꂽ�W���͂��A�S�̂ɖ��ՂȂ��o����悤�ȓw�͂�H�v�ŁA12���Ԃ̉��y�G�}�����I�ɑN�₩�ɂȂ�͂��ł��B�������A�w���w������A�悭�撣���Ă܂����I |
| 12: �k���x���@�x�R����\�@�x�R��w���t�y�c ��� �i�w��:�����m�O�j3�N�A��6��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�������́`�O�̈قȂ�\���Ł`�i�������)�ۑ�Ȃ́A��⎕��̈����}�[�`�Ƃ�����ۂŁA�e���|�ݒ�ɖ�肪�����������m��܂���B�A���T���u�����S�̓I�ɐ��ʂ������A�����Ƒΐ����̃o�����X�Ɉ�l�̗]�n����ł��B�ł��C�ɂȂ����̂̓X�l�A�h�����̃`���[�j���O�Ƃ������A������X�l�A�̒����ł��傤���B�}�[�`�S�̂��d���Ȃ�v���̂ЂƂɂȂ��Ă����悤�ł��B���R�Ȃ́A2�{�̃g�����y�b�g�ɂ��o���_����X�^�[�g���郆�j�[�N�ȋȁB�u��l�̃`���M�X�E�n�[���v�Ƃ������悤�ȕ��͋C���������y�Ȃł����A���t�ʂł̓o���h�S�̂̃T�E���h�ɍX�ɃN���A�����~���������Ƃ���B�w������̂ƂȂ��āA���X�A�i���[�[����K�����A��w���ɂȂ�ΕK�v�����m��܂���B�������A�k���̃o���h�̃u���X�̋����̂���т₩���́A���݂ŁA�l�I�ɐS�n�悢���̂������Ă��܂��܂��B |
| 5: ���C�x���@�É�����\�@�É���w���t�y�c ���� �i�w��:�O�c�����j2�N�A��12��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:���l�̌��ɂ̂����iP.�O���n���j�����̎w���҂��X�e�[�W�ɓo�ꂷ��ƁA�A�����J�̃A�j���̂悤�Ȗ��邳�������܂��B���āA�ۑ�Ȃ̃}�[�`�͑S�̂�ʂ��Ă��G�R�Ƃ��Ă��銴���ŁA�y��ɂ���ċZ�ʂ̃o���c�L���傫���̂��A�����̈����y�킪�U������܂����B�y�����Č�������ɁA�ǂ�ȃ��b�Z�[�W�����y�ɍ��߂�̂��A���������A�v���[�`���~�����Ƃ���ł��B���R�Ȃ́A��͂�ׂ����t���[�Y�̃o�������C�ɂȂ�܂����B���e���E�e�C�X�g�����������y�ɂ����ẮA�T�E���h�̂��˂�≹�y�I�ȗd�������A�~���������Ƃ���ł��B |
| 6: ��B�x���@��������\�@������w�����w�������t�y�c ���� �i�w��:�ԉ������j2�N�A��31��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�u�A�����J�̋R�m�v���A�I�ꂵ���iS.�������j���t�O�́A�Z�b�e�B���O�̒x�������C�ɂȂ�܂����B�ۑ�Ȃ́A�y�Ȃ̗v�f�͂�������ƍČ�����Ă��܂������A�S�̓I�Ƀ����n�����������}�[�`�ɂȂ��Ă����̂��c�O�B���F���_�[�N�C���ŁA���y�ɍ��킹�����F�̌������K�v�ł��傤�B���R�Ȃ́A�킵���T�b�N�X�̃\������X�^�[�g�A�G���L�x�[�X���g���Ȃ��Ȃ��Ă���v�X�̓o��Ȃł��ˁB���������Ɠ����o�����X�����Ȃ�A���o�X�́A�Œ�ł�4�{�K�v�Ȃ̂ł͂ƁA�����Ă��Ċ����܂����B���������Ӗ��ŁA�ቹ���������ɂȂ��Ă��܂������͔ۂ߂܂���ł����B���y�ɂ��X�Ƀ^�C�g�����~���������Ƃ���ł����A�؊ǂ̃T�E���h���������A�������ۗ������D���������Ǝv���܂��B |
| 7: ���k�x���@��茧��\�@����w���t�y�� ���� �i�w��:���n���V�j28�N�Ԃ�14��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�����ȑ�3�Ԃ��A��3�E4�y���iJ.�o�[���Y�j�ۑ�Ȃ́A���y�����R�ŁA���̕\�������ƂȂ��߁A�Ƃ�����ۂ������ł��傤���B�}�[�`�ɂ����Ă̓g���I�ŃT�E���h�≹�y�ɂǂ��ω���t���邩�������Ƃ���ł����A���̂܂܂̐����œ˂������Ă��܂��܂����B�A���T���u�����A�X�Ȃ�b�����K�v�Ȃ悤�ł��B���R�Ȃ́A3�y�͂̎�t�ɕs���肳�������܂����B4�y�͂ł́A�g�D�b�e�B�ɂ�����T�E���h�ɑ��肪�U�����ꂽ�̂��c�O�ł��B�������A�T�E���h���̂��̂̓_�C�i�~�b�N�����W���L���A�S�n�悢�����������Ă���̂ŁA���ꂩ�特�y�I�ɂǂ������������čs���̂��A�y���݂ɂ��Ă������Ǝv���܂��B |
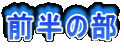 |
| 3: ���k�x���@�H�c��\�@��Ȑ��t�y�c ���� �i�w��:���ˁ@�ށj3�x����16��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�o�b�n�̖��ɂ�錶�z�Ȃƃt�[�K�iF.���X�g�^�c�������j�����O�̏d���ȃT�E���h�ŃX�^�[�g�����ۑ�Ȃł������A���d���}�[�`�Ƃ�����ۂŁA����͑����ቹ�ɏd�S��u�����T�E���h��肪�e�����Ă����̂����m��܂���B�T�E���h���̂��̂ɂ��A�}�[�`��t�ł�ɂ������ẮA�X�ɃN���A�����~���������Ƃ���ł��B�X�ɋ��NJy��ɉ��݂����Ȃ��̂������ƁA���ӂ肪�i�i�ɗǂ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���R�Ȃ͈�]���āA���̃T�E���h���y�Ȃɒ��ǂ��}�b�`�����D���ł����B�؊NJy�킪�X�ɃV���t�H�j�b�N�ȋ��������ƁA�F�ʊ������������ł��傤�B�t�[�K�̍��g�݂ɂ͍X�Ȃ�A�i���[�[���~���������Ƃ���ł����A�S�̂�ʂ��āA�������x���̃A���T���u�����S�n�悢���E�ς����グ�Ă����Ǝv���܂��B |
| 6: ���C�x���@�É�����\�@���}�n���t�y�c�l�� ���� �i�w��:�{��W��j3�x����38��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�u�A�C�E�K�b�g�E���Y���v�ϑt���iG.�K�[�V���C���^���������j ���̂Ƃ��뉡�j���o����葱���Ă��銴�̂���o���h�ł��B�d���Ȃ�����N���A�ȃT�E���h�͌��݂ŁA�S�̂�ʂ��ĉ��y���X�b�L���ƕ������Ă��܂����B�܂��ɋ}�̃^�C�~���O���▭�ŁA�Ƃ�����Ζ��@���ɂȂ肪����5�ԂɁA�����ɖ����h�点�Ă����̂Ɋ������܂����B���X�g�̗�̉��̓X�e���I���ʂ����鉉�o�ŁA�~���[�W�b�N�E�J���p�j�[�Ȃ�ł͂̐S�������o�ł����B���R�Ȃ͐��E�ς��K�����Ƒ���A���킹�ăT�E���h���K�����ƕϖe�������̂͗��ł��B�z�[���̔����̉e���Ȃ̂��A�r���ł��Y���̊��ݍ���Ȃ������������܂������A�ׂ����t���[�Y�̍Č��͂͌����ŁA�V�ѐS�����ڂ̗]�T�̉��j���o�����N�����\�����Ē����܂����B |
| 8: ���֓��x���@�_�ސ쌧��\�@���l�u���X�I���P�X�^�[ ���� �i�w��:�ߓ��v�ցj2�N�A��10��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�j�T����(J.�C�x�[���^�ߓ��v��)�`���̏d���ȃT�E���h�͌��݂ŁA�}�[�`���ǂ̂悤�ɉ��o����̂������ÁX�ł������A���y�����ɃN���A�ŁA�S�Ă̗v�f���ߕs�������Č����Ă����̂ɂ͒E�X�ł����B���Ƀg���I�����̃h���C�u���͒������́I�����A�x�[�X���C���̏������A���V���t�H�j�b�N�߂������߂��A������}�[�`�Ƃ��Ă̑O�i�͂������鎖���o���Ȃ������̂������c�O�ł����B���R�Ȃ́A�ׂ��������̒��ł��u���Ȃ��n�[���j�[���f���炵���A�������Ɉ�ꂽ�A��̗ǂ����y��W�J���Ă��܂����B���x�ȃ��x���̃A���T���u�����▭�ł������A�I�Ղ�≹�y���G�R�Ƃ��Ă��܂����̂������c�O�ł����B���̏j�T���Ȃ͎��̃t�F�C�o���b�g�\���O�̂ЂƂB�C���[�W�ʂ�A���₻��ȏ�̉��t�ɑ����o�����K���Ɋ��ӂ������Ǝv���܂��B |
| 9: �����x���@�����s��\�@�n���O�����A���t�y�c ���� �i�w��:�����r�Y�j4�N�A��22��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�o���G���y�u�����̕s�v�c�Ȗ�l�v����iB.�o���g�[�N�^���V�r�N�j�d���ō����Ȃ�����@�ׂȕ����������獇�킹���T�E���h�́A�S���{�̃X�e�[�W�ł����݂ł����B�܂��T�E���h����������ƃu�����h����Ă���̂ɕ������ǂ��Ƃ����Ɠ��̋����́A���̒ǐ����������Ƃ͂��炭���������ł��B�ۑ��5�Ԃ́A�������܂ł�������ƃA�i���[�[����A�Ɍ��܂ł�����Č����悤�Ƃ����t�҂����̌����͂܂��ɉ��y�̗E�҂��̂��́B�����ė��̓I�ɉ�����ь����A���T���u���͂̍������A�����Ɋy���܂��Ē����܂����B���R�Ȃ́A��ԋȂł����A��荂�x�ȃA���T���u�����S�n�悭�A���芴���Q�̉��y��W�J�����Ă��܂����B�����A���芴���Q�ł��邪�䂦�ɁA�X�ɖ`���S���������I�Ȃ����������Ǝv���̂́A�I�[�f�B�G���X�̐g����Ȋ肢�ł��傤���B |
| 11: ���֓��x���@��ʌ���\�@��z�t�a�t�F��t�y�c ���� �i�w��:�������l�j2�N�A��14��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�u���t�y�̂��߂̑g�ȁv���A1.�t�@���t�@�[�� 2.�q��� 3.�J�v���`�I(�e�r�K�v)�ق��̃o���h�Ƃ͈�����悵���X�e�[�W�̃Z�b�e�B���O�ɂ܂��͖ڂ�D���܂����B�]�T�̂��鉹�ʂŌJ��L�����ۑ��5�Ԃ́A���y���A�i���[�[����Ƃ������̊y������`���悤�Ƃ��邩�̂悤�ȉ��o�ŁA���̃o���h�Ȃ�ł͂̓Ǝ����𐏏��Ɋ���������A��l�̉��߂���������i�Ɏd�オ���Ă��܂����B�܂��A�NJy��̌��Ԃ�D���Č���Ă���Ŋy��̑��݊����A�S���{�̕���ɂ����Ă��V���Ȕ������_�Ԍ�����Ƃ����̂́A�I�[�f�B�G���X�̑�햡�̂ЂƂł��B���R�Ȃɂ����Ă��A�d���Ȃ�����N���A�ȃT�E���h�͌��݂ŁA���y�ȑO�ɃT�E���h���̂��̂��������Ă���̂ɖڂ�D���܂����B�͂�킽�ɋ����Ă���d�S�̒Ⴂ�T�E���h�����A��l�̃o���h�Ȃ�ł͂̒B�����Ȃ̂��ƁA���߂Ċ��������Ă���܂����B |
| 1: ���k�x���@�{�錧��\�@��V���t�H�j�b�N�E�B���h�I�[�P�X�g�� ��� �i�w��:�r��x�Y�j2�N�A��6��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�V���O�E�E�B�Y�E�V���Z���e�B�[�i�����~�j�d���ŕ����ʂ�V���t�H�j�b�N�ȃT�E���h�������Ă���n���h�ł����A���̂������ۑ�Ȃ͂��d����ۂ̃}�[�`�ɂȂ��Ă��܂����B�܂��A�T�C�`�̏o�������e�����Ă��A�T�E���h�������C���������悤�ł��B�܂��A���y�I�ɂ��X�Ȃ�A�i���[�[�̗]�n������悤�Ɍ����܂����B���R�Ȃł́A��͂�T�E���h�ɃN���A���������Ă����������A���y�I�i���͂Ɍ��������t�ɂȂ��Ă��܂����悤�ł��B�o���h�̃T�E���h�����I�Ȃɂ���āA�X�ɕ]����������̂ł́A�Ƃ����������܂����B |
| 4: ���x���@�ޗnj���\�@M's Sound Factory ��� �i�w��:���؍G�V�j���o�� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�̌��u�g�X�J�v����iG.�v�b�`�[�j�^��؉p�j�j�ۑ�Ȃ̖`������X�l�̉��t�Z�p�̍����������܂����B���l���ł��镪�����A�T�E���h���N���A�ŁA�i�`�������ȉ��y��t�łĂ����̂���ۓI�ł����B�����A�}�[�`�Ƃ��Ă̑O�i�͂͏[���Ɋ�����ꂽ�̂ł����A�n�[���j�[���ł��A�����Ƃ̃u�����h�������܂ЂƂs�����Ă����悤�ł��B���R�Ȃł��A���̍����A���T���u���͂͌��݂ŁA�����̉̂��������ɉ��y�I�Ȃ��̂������܂����B�����ΐ����̏����A�僁���Ƃ̗��݂������ЂƂŁA�t�̈Ӗ��ʼn��y���킩��₷�߂���Ƃ�����ۂ��܂����B����l���������ăT�E���h�≹�y���ǂ��ϖe���čs���̂����A�y���݂ȃo���h�ł��B |
| 5: ��B�x���@����������\�@J.S.B�D���t�y�c ��� �i�w��:���@�v�Ɓj2�N�A��8��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�����I��ہu����̃X�e���h�O���X�v����iO.���X�s�[�M�^���c���d�j�ۑ�Ȃ̖`������A�d���ŃN���A�A�������̗ǂ��T�E���h�ɐS�n�悳�������܂����B���肵���n�[���j�[���A�ۑ��5�Ԃ����₩�ȉ��y�Ɏd���ďグ�Ă����悤�ł��B�����S�̂ɂ܂����芴���������邫�炢������A�����ʼn��y������Ă��܂����̂��c�O�ł��B���R�Ȃ́A�`���̌��o�X�̃T�E���h����A�y�Ȃ̐F�ʊ����E�ς����܂����o�����D���ł����B�����̉̂������A��l�Ȃ�ł͂̉��₩���������Ă����Ǝv���܂��B���������ł����y���S�̓I�ɏ疟�ŁA�X�Ȃ��M���قƂ��镔����A�V�[�����Ƃ̉��F�̕ω������~���������ȁA�Ƃ�����ۂł����B |
| 7: ��B�x���@��������\�@�t���s���t�y�c ��� �i�w��:���q���Ɂj24�N�Ԃ�5��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�G���K�[�E���@���G�[�V�����iM.�G���r�[�j�ۑ�Ȃ́A�T�E���h���ł߂ŁA�\��ɖR�����}�[�`�Ƃ�����ۂł����B�����~�X���U������A�A���T���u�����s���ȕ���������������ꂽ�͎̂c�O�ł����B����Ȓ��ł��A�o���h���̂��̂̃T�E���h�́A�����W���L���S�n�悢���̂��������Ǝv���܂��B���R�Ȃł��A���y�I�Ȑ������t���Ă��Ȃ��͖̂����ŁA�i���͂Ɍ����鉉�t�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����������Ɖ̂��ĕ�������H�v���{���Ă��炢�������̂ł��B |
| 10: �l���x���@���m����\�@���쐁�t�y�c ��� �i�w��:�O�c�����j4�N�A��22��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�։�̔����`�m�E�`�E��E�q�E���E�M�E�F�E��`�i�M���듿�j�܂��̓T�E���h���A��l�̃o���h�Ƃ��Ă͐����ׂ����ȁA�Ƃ�����ۂ������܂����B�S�̂̃u�����h�������܂ЂƂŁA���y�����G�R�Ƃ��Ă��܂����悤�ł��B�n�[���j�[�����N���A�ɋ������ė~�����������ȂƂ�����ۂł����B���R�Ȃ́A�y�Ȃ̃I�[�P�X�g���[�V��������`���āA�T�E���h�̓K�����ƃN���A�ɕϐg�B�����ቹ�͂����Əo�Ă��Ă��o�����X�I�ɗǂ����������m��܂���B�܂��A�ׂ����t���[�Y�ɂ����āA�ǂ��ɃA�N�Z���g�������Ă��邩�A���������\���ׂ̍₩���݂����Ȃ��̂��~�����Ƃ���ł����B |
| 2: �k���x���@���䌧��\�@�\�m�[���E�E�B���h�E�A���T���u�� ���� �i�w��:�I�c����j3�x����9��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�������́`�O�̈قȂ�\���Ł`�i�������j����דI�ȃC���g������X�^�[�g�����}�[�`�ł������A��͂肻���͎��R�ȗ�����ɂ��ė~�����Ƃ���ł��傤�B�T�E���h�̓N���A�ň��肵�����̂����������܂������A�S�̂�ʂ��Ď���̈������t�ŁA�}�[�`���d����ۂɂȂ��Ă��܂����悤�ł����B���R�Ȃ́A�z�[���̋����������D���ŁA�T�E���h�͂��N���A�ɂȂ�A���肵���n�[���j�[���S�n�悢���̂������܂����B���̊y�Ȃ��悭�������A�i���[�[���{�������߂������Ǝv���܂��B�X�ɁA�������ۗ����o������A���y���̂��̂��N���A�ɓ͂����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |
| 12: �k�C���x���@�D�y�n���\�@�D�y�u���X�o���h ���� �i�w��:�ēc�_�Ɓj���o�� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�~���[�W�J���u���E�~�[���u���v����iC.M.�V�F�[���x���N�^�����O�a)�T�E���h���S�̓I�ɔ����s���ĂŁA���y�Ƀ����n���������Ă��܂��܂����B�S�̓I�ɒW�X�Ɖ��y���i�s���čs�������āA������l�̃X�p�C�X�݂����Ȃ��̂��{���ė~���������Ƃ���ł��B���R�Ȃ́A�������Ɖ̂������ł͂��̖{�̂����Ă����悤�ł����A����ȊO�̕����ł̏�ʂ��Ƃ̃T�E���h�̕ω���A���y�I�ȃ����n�����A�~���[�W�J���̊y�Ȃ����t����Ӗ��݂����Ȃ��̂�Nj����ė~�����������ȁA�Ƃ�����ۂł����B |
| 13: �����x���@�L������\�@NTT�����{�������t�y�N���u ���� �i�w��:���c�N�F�j2�N�Ԃ�46��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�Z���g�E�A���\�j�[�E���@���G�[�V�����iW.H.�q���j���邢�T�E���h�ɂ��O�i���̂���}�[�`���S�n�悳�����o���Ă��܂������A�T�E���h�ɂ�⏁�����s�����Ă����̂��c�O�ł����B�����n���ɂ���⌇���Ă����悤�ł��B���R�Ȃ́A���y�̍��g�݂��悭�킩��A�A�i���[�[�̂悭�{���ꂽ�D���ŁA�����A���T���u���͂������Ă��܂����B�I�Ղ͂�⑧�ꂵ�Ă��܂�����ۂŁA�t�@���t�@�[����t�[�K�̉��o�ɁA�X�Ȃ��l�̏�����������ė~���������Ƃ���ł��B�������A�T�E���h�����y���N���A�ȉ��t�ɑ��铺�܂͏��X�����ȁA�Ƃ�����ۂ������܂����B |
 |
| 1: ���֓��x���@��ʌ���\�@����s�E�A���T���u�����x���e���t�y�c ���� �i�w��:���{�M���Y�j4�N�A��18��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�o���G���y�u�����̕s�v�c�Ȗ�l�v���(�a.�o���g�[�N�^���{�_�K)�ۑ�Ȃ̖`�����炻�̃T�E���h�����邱�ƂȂ���A���y�I�ȏ��������ɗ��̓I�ɂȂ���Ă���̂���ۓI�ł����B���̃o���h�͓��ɖ؊ǂ̋������L���ŁA���ǂƃu�����h���ꂽ���ɁA�S�̂̃T�E���h�ɗh�炬�������炵�Ă���̂ɂ�����������܂��B�y�Ȃ̑S�Ă̗v�f���ߕs���Ȃ��Č����A�����W�̍L���T�E���h�ƍ����A���T���u���͂��A���y�������X�e�[�W�ɏ������Ă���̂ł��傤�B�T�E���h���̂��̂��l�X�ȃJ���[�������Ă���̂��A���y���X�ɕ\��L���ɂ��Ă����悤�ł��B���R�Ȃ́A�R���N�[���̒�ԋȂł����A�؊ǂ��[�������o���h�ł̃o���g�[�N�͂܂��V�N�ȋ����Ɣ����������炵�Ă��܂����B���j�]���̐��x���f���炵���A���̐��E�ɂ܂��ɖv���������Ă��܂���12���Ԃł����B |
| 2: ���C�x���@�É�����\�@�l���������t�y�c ���� �i�w��:��c�@���j4�N�A��13��� �ۑ��3: �u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j ���R��:�P���������`��ہA���s�A�Β�A���t���i�^���r�v�j����т₩�ȃu���X�T�E���h���A���̉ۑ��3�Ԃ̃C���g���ɉ₩����Y���ẴX�^�[�g�ł����B�`���̎��́A�Z�O�����g���Ƃɉ��F�̕ω��������Ɖ��o���ė~���������Ƃ���ł����A�S�̓I�ɂ̓A�i���[�[�̍s���͂����A�D���������Ǝv���܂��B�����A���j�]���̐��x���Â��A���ܒ@������悤�ȃT�E���h�̏���������ꂽ�̂��c�O�ł����B�I�Ղ̐����Ƒΐ����̃o�����X�ɂ��A�ׂ����C�z�肪�~���������Ƃ���ł��B���R�Ȃ́A���̃o���h�炵����ʑI�ȂŁA�ǂ�ȏ������{���Ă���̂��y���݂ɂ��Ă��܂������A���NJy��̉s�p�I�ȃT�E���h���A���̊y�ȂɐV���Ȗ��͂�Y���Ă��܂����B�����ăA���T���u���̃��x���������G���ł������A�n�[���j�[�̏d�˕����ɂ͂��@�ׂȐS�z�肪�~�����������ȁA�Ƃ�����ۂł��B |
| 7: ���x���@���{��\�@�n���w������t�y�c ���� �i�w��:�ɐ��q�V�j3�N�Ԃ�16��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�O�̃W���|�j�X���i�^���r�v�j�ۑ�Ȃ̖`���A��u�A���T���u���̗��ꂪ�����A�h�L���Ƃ������܂������A���̌�͈��肵���}�[�`��W�J���Ă��܂����B�T�E���h�����y���d���ł������A�S�̓I�ɉ����������Ă��銴���ŁA�S�̂�ʂ��Ė��������������Ȃ������͎̂c�O�ł��B�܂��A���y�����J���C���ł������A�����I�ɂ̓^�C�g�Ȃ��̂������Ă������̂��ȁA�Ƃ�����ۂł����B���R�Ȃ́A�����A���T���u���͂ŁA�]�T�������ĉ��y�������Ă��܂������A���������y�Ȃł̓T�E���h�≹�y�̂��˂�݂����Ȃ��̂��~���������Ƃ���ł��B�܂����������ܖ�����Ă��܂������ɂȂ镔��������A���˂������y�̍\�z��A��l�Ȃ�ł͂̐�����搂����ݓ����A�����Ƃ����Ă������ȂƊ����܂����B�Ƃ͂����A����͍������t�͂��������o���h�Ȃ����Ɏv���Ă��܂��A�������̍X�Ȃ�䂪�Ԃł�����킯�ł����E�E�E�E�B |
| 11: ���k�x���@�{�錧��\�@����������t�y�c ���� �i�w��:�k ���ׁj3�N�A��19��� �ۑ��5:���݂͗ь�̎���A�����i�J�n�����l�j ���R��:�A�X�t�@���g�E�J�N�e���iJ.�}�b�L�[�j�d���ŖL���ȋ������������T�E���h�ɂ��ۑ�Ȃ́A�`�������≹�y�����ʓI�ɂȂ��Ă��āA�܂��܂��A�i���[�[�̗]�n������̂ł͂Ȃ����ȁA�Ƃ�����ۂł����B���ʂ��������x���ōČ����邻�̉��t�͂ɂ͑f���炵����������̂ł����A�y�ȑS�̂��ǂ̂悤�ȃX�g�[���[�Ŗa���ł����̂��A���������A�v���[�`�܂ł͒B���Ă��Ȃ������̂����m��܂���B�������A�S�̂�ʂ��ăT�E���h�̃o�����X���ǂ��A�����A���T���u���͂��������D���ł����B���t�͂ƌ����A���R�Ȃ͂��̃v���X�ʂ������ɐ������������ł����B���������ŃI�[�o�[�t���E�C���ɂȂ��Ă��܂���������������A�h�^�o�^���Ă��܂��������������킯�ł����A�t�҂����̃G�l���M�[�̋����͑f���炵���A���t��͈������̔��芅�т𗁂тĂ��܂����B���̏W���͂ɂ��E�X�ł��BCD��c�u�c�����\��̕��X�͊y���݂ɂ��Ă��ĉ������I |
| 3: �����x���@�����s��\�@�����������t�y�c ��� �i�w��:���c�M���j4�N�A��4��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�t�F�X�e�B�o���E���@���G�[�V�����iC.T.�X�~�X�j�Ⴂ�����Ƃ����T�E���h�Ƃ����̂����̃o���h�̃C���[�W�ł������A�ۑ�Ȃ͑�l�̃}�[�`�Ƃ������ł����ŁA���ቹ�̋������ɂ����A���芴�̂��鉹�y�ł����B�����A��╂�V���������A�n�ɑ����t���������A�^�C�g�ȕ���������A���y�S�̂����܂����̂ł͂Ȃ����ȁA�Ƃ�����ۂł����B�������A�����O�i�͂����������y���́A���̃o���h�̈������̃p���[�[���Ɋ�����������̂ł����B���R�Ȃ́A������Y���̓�Փx�������y�Ȃɒ���B�������悭�������A���g���𐏏��ɔz�����A�S��鉹�y�����o���Ă��܂������A�}�[�`����̓]���ɂƂ܂ǂ����t�҂��U������A�`�������Ń��Y����A���T���u���ɁA�ق���т������Ă��܂����̂��A�c�O�ł����B���A���������`�������W���_�ɂ͑傫�Ȕ���肽���Ǝv���܂��B |
| 4: �k�C���x���@�k���n���\�@�k�����t�y�c ��� �i�w��:���c�����j2�N�A��6��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�����i�ۉȗm�j�ۑ�Ȃ́A�u���X�T�E���h�����A�ŁA�n�[���j�[�j�ɑ��肪�����Ă��܂��Ă����̂��c�O�ł����B�K�x�ɃA�i���[�[���{���ꂽ�A���肵���A���T���u���́A�S�n�悳������Ă��܂������A�����I�Ɏ��ɂ��T�E���h���������y�킪�����������܂����B���̕ӂ̉��y�I�T�E���h�I�����́A��l�̃o���h�Ƃ��Ă͂�������Ǝ{���ė������炢�����Ƃ���ł��B���R�Ȃ́A�����ł����肵���A���T���u���������Ă��܂������A�S�̓I�ɉ��y�����R�ɂȂ��Ă��܂�����ۂł��傤���B�I�Ղ́A�X�ɑ�l�Ȃ�ł͂̉̂����������ėǂ������̂ł͂Ȃ����ȁA�Ǝv���܂����B |
| 5: ���֓��x���@��t����\�@���E�B���h�I�[�P�X�g�� ��� �i�w��:�����@���j2�N�A��2��� �ۑ��1: �ʼnʂĂ̏�̃[�r�A�i�����p��j ���R��:�����̌��̋P�{��(�M���듿)���Ƀ����W�̍L���T�E���h���S�n�ǂ��A�������܂ł�������ƃA�i���[�[���{���ꂽ�A�����A���T���u���͂́A���܃o���h�ɕC�G������̂������Ă����Ǝv���܂��B��t�����肵�Ă��āA���������z�[���̒��ł��A�K�x�ɃT�E���h�ɉ����������鎖�ɐ������Ă����u���X�̋�������ۓI�ł����B���R�Ȃɂ����Ă��A���肵���n�[���j�[�A�u���Ȃ���t���A���y�S�̂Ɏ��R�Ƀ����n����^���Ă��܂����B��̃P�A���X�~�X���c�O�������̂ƁA�S�̂�ʂ��Ēቹ�T�E���h�����������o�����X�I�ɑ傫����������ƁA�����芴���������̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂����B |
| 8: ���֓��x���@�_�ސ쌧��\�@�O���[���E�B���h�I�[�P�X�g�� ��� �i�w��:���쐹��j3�N�Ԃ�9��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�g���W�`�j�E�\�i�^�E�i�E�W�����o�J�E�C�E�v�E�H�[���G(�V�쐳���j�����W�̍L���N���A�ȃT�E���h���������o���h�ł����A�ۑ�Ȃ́A6/8�̃r�[�g�ɂ��s���R���ƕs���肳�������܂����B�܂��X�l�A�ƁA�NJy��Ƃ̃R���{���[�V�����A�R���r�l�[�V�����ɂ��ۑ肪�������悤�ȋC�����܂��B�܂������ɂ��A��ʂɂ���Ă��܂��܂ȕ\��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��Ă��傤���B���R�Ȃ́A�`���J���~�i�u���[�i�̂悤�ȓW�J��������y�Ȃł����A�n�[���j�[�����X�J�b�Ƃ����A�G�R�Ƃ������y�ɂȂ��Ă�����ۂł����B�T�E���h���̂��̂ɂ��A�������������y�Ȃ������鎞�ɂ́A���G�b�W���~���������Ƃ���ł��B���j�̂���o���h�ł�����A����͂܂��K�����ƌ��Ē����āA�u���ȉ��y�����Ă���鎖�ł��傤�B |
| 10: ��B�x���@��������\�@�ђː��t�y�c ��� �i�w��:�J���@���j3�N�A��3��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�I���G���^���Y���[�h2014�`�E�C���h�I�[�P�X�g���̂��߂��i�Љ������j�ۑ�Ȃ̖`������A���ɂ܂�₩�ȃT�E���h���������o���h�Ƃ�����ۂŁA�ቹ�̍��݂����ɐS�n�悢�}�[�`�ł����B�������A�؊ǂ̃��j�]���ɂ��u�����U�����ꂽ�̂ƁA�����n�����ʓ]�������܂芴����ꂸ�A�����ł��̂܂ܓ˂������������������͎̂c�O�B���R�Ȃł́A���̂܂�₩�ȃT�E���h�̂��߂��A�S�̂���������Ƃ�����ۂɂȂ��Ă��܂��܂����B�܂�₩�Ȓ��ɂ��A��ʂɂ���Ă͉s�p�I�ȃT�E���h���A���̎�ނ͖L�x�ɗ~�����Ƃ���ł��傤�B�܂��X�R�A�ɂ͌���Ă��Ȃ����̓I�ȉ��y���Ƃ����̂��A���ꂩ��̃��x���A�b�v�ɂ͕K�v�ƂȂ��čs���̂ł͂Ȃ��Ă��傤���B |
| 13: ���x���@���Ɍ���\�@��ˎs���t�y�c ��� �i�w��:�n�ӏG�V�j2�N�A��8��� �ۑ��4:�R���T�[�g�}�[�`�u�t�̊X�Łv�i���ѕ��v�j ���R��:�����i�ۉȗm�j���ɂ܂�₩�ȃT�E���h���������o���h�ł��B���A����̓`���[�o�𒆐S�Ƃ����ቹ�y��Ƃ���ȊO�̃T�E���h�Ƃ̃u�����h�������܂ЂƂŁA��ʂɂ���Ă͍X�Ȃ�G�b�W���������������~�����Ƃ���ł����B�B�S�̓I�ɉ��y���s���Ăȃ}�[�`�ɂȂ��Ă��܂����̂��c�O�B���R�Ȃ́A�����x�̍����A���T���u�����A�y�Ȃ̃C���[�W��I�m�ɕ\�����Ă��܂������A��͂�T�E���h�̃o�����X�����܂ЂƂŁA�؊ǂ���̂ɂ����o���h�ł͂�����̂́A�u���X�T�E���h�������Ɨ~�������ȂƂ�����ʂ����т��ь����܂����B���Ոȍ~�̓o�����X���ǂ��Ȃ�A�N�₩�ȃA���T���u���ŐV�����̃g������߂Ă���܂����B |
| 6: �k���x���@�x�R����\�@�x�R�~�i�~���t�y�c ���� �i�w��:�q��@���j5�N�Ԃ�5��� �ۑ��2:�s�i�ȁu�E�C�̃g�r���v�i�����G���j ���R��:�R���T�[�g�o���h�ƃW���Y�A���T���u���̂��߂̃��v�\�f�B�iP.�E�B���A���Y�^S.�l�X�e�B�R�j�ۑ�Ȃ́A�T�E���h�ɃN���A���������Ă��邽�߂��A���ꂪ�����A�������͂��ė��Ȃ��A���r���[�ȃ}�[�`�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�S�̂̃A���T���u�����A�����肳�������Ă����ł��傤���B���R�Ȃ́A�������������e�C�X�g���D���Ȃ̂ł��傤�A��]���āA4�r�[�g�̐��E�ς��ӂ�ɕ\������D���ł����B���Ƀg���[���{�[���𒆐S�Ƃ����z�[���E�Z�N�V������Jazzy�ȗh�炬�́A�▭�ɐS�n�悢���̂�����܂����B�T�b�N�X�A���T���u���͂����ƃr�u���[�g����g���āA�W���Y�̐��E�ς�ł��o���Ă��ǂ����������m��܂���B��l�̃o���h�ł�����A�܂̐F�����A�ǂꂾ���Ɍ��܂ł��̐��E�ς����o���A�Z��邩�A�������������ɂ����Ƃ����ƒ���ł��炢�������̂ł��B���o�X�͂���2�{���炢�����Ă��A�ǂ����������m��܂���B�l�I�ɔ��Ɋy���܂��Ē��������R�Ȃł����B |
| 9: �l���x���@���Q����\�@�����吪�Ƃ䂩���ȉ��y���Ԃ��� ���� �i�w��:�����吪�j4�N�Ԃ�2��� �ۑ��3: �u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j �R��:���b�L�[�h���S���`��ܕ����ۂ̋L���i�����O�a�j��������Ƃ����T�E���h����X�^�[�g�����ۑ�Ȃ́A���e���|�����߂��銴���������ł��傤���B���̂��߂��A���y�ɃG�b�W���Ȃ��s�N���Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��܂����B�n�[���j�[�ɂ��X�Ȃ���芴���~���������Ƃ���ł��B���R�Ȃ́A���芴�̂���A���T���u���ƁA�d���ȃT�E���h���悭���������D���ł������A�S�̂�ʂ��āA�S�Ă̗v�f���荇���Ă�Ƃ��������ŁA��蒚�J�ȃo�����X���{���Ă��炢���������ȁA�Ƃ�����ۂł����B |
| 12: �����x���@�L������\�@�L���V���t�H�j�b�N�E�t�@�~���A���t�y�c ���� �i�w��:�È�ː��ȁj���o�� �ۑ��3: �u�֑��Y�߁v�̎��ɂ�錶�z�i���c����q�j�@�@ ���R��:�傢�Ȃ�̑�n�`�`���M�X�E�n�[���i��؉p�j�j�w���҂́A�L�����̒��w�Z�̐搶�ł����A���̃o���h�����C�������w�Z�̑��Ɛ��ȂǂŕҐ�����Ă���̂ł��傤���B�ۑ�Ȃł́A�����A���T���u���͂ƁA��������t�����݂����A�����ʂ�V���t�H�j�b�N�ȋ��������T�E���h�Ɏ䂫���܂�܂����B�ۑ��3�Ԃ̃e���|�ݒ���▭�ŁA�����̉̂������f���炵�����y�����グ�Ă��܂����B���R�Ȃł��d���ȃT�E���h�͌��݂ŁA���ɒ����S������y��̈��芴�����Q�Ȃ͍̂���Ɋ��҂����Ă�Ƃ������́B�����A���̎��R�Ȃɂ����ẮA��l�Ȃ�ł͂̉��߁A�i���͂������Ă��A�Ƃ����������������ǂ��������ȁA����A�����ė~���������ȂƎv��������ł��B |