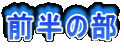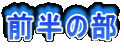 |
4: �����x���@��������\�@�o�_�s����ꒆ�w�Z �i�w��:�i�@�^��j ���� 2�N�A��43���
�ۑ��3:��VIII-���x�̂��߂̃w�e���t�H�j�[�i�����N�j
���R��:�����g�ȁu��`�n�v���A�`���j�X����l�t�^�A���@�����V�A�iJ.�C�x�[���^P.�f���|���j���ɏ[���������x�̍����A���T���u���ƁA�_�C�i�~�b�N�����W�̍L���T�E���h���A�z�[�������ς��ɋ����킽��܂����B�ۑ�Ȃ́A��������ƃA�i���[�[���{����A�����n�����K�x�ɕt�����D���ł������A�܂��A�i���[�[�̗]�n���c����Ă������ȁA�Ƃ�����ۂł��B���R�Ȃ́A�n���ɉ��y��ςݏd�˂Ă����̂��N�b�L���Ƃ킩�閼���ł����B�T�E���h�̃o�����X�A�X�̉��t�͂̍����A�����Đ▭�ȃA���T���u���A�S�Ăɂ����Ă��̊y�Ȃ̎����͂��\���ɕ\�����`���鉉�t�������Ǝv���܂��B�\���̕\���͂��L���ŁA�Ȃ�Ƃ����Ă����y���f�����������ĕ\������Ă����̂Ɋ������܂����B |
5: ���x���@���{��\�@���s����A���w�Z �i�w��:��@�R��j ���� 2�N�A��2���
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:�������u���[�}�̍Ղ�v���A�`���`�F���Z�X�A�匰���iO.���X�s�[�M�^�X�c��_�j��⑁�߂̃e���|�ŃX�^�[�g�����ۑ�Ȃ́A��������������ƕ�����������A�i���[�[�͂��f���炵���A�������\���Ȕ����Ƃ����}�[�`�Ɏd�オ���Ă��܂����B����Ȓ��ŁA���j�]���̐��x�ɂ��u��������ꂽ�̂��c�O�ł����B���R�Ȃ́A���̃o���h�̉��t�͂��֎����閼���ŁA�o���_�̊����x�A�ׂ����t���[�Y�̍Č��́A���j�]���̐��x�̍����A�S�Ă������w�����̂��̂������Ǝv���܂��B�ׂ������̓���������悭�������A��M�I�ȍՂ�̐��E�ς𗧑̓I�ɖ�����̂ɐ������Ă����ƌ����Ă����ł��傤�B |
7: ���֓��x���@��t����\�@���s�����䍪���w�Z �i�w��:���˒��_�j ���� 2�N�A��11���
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:�V���ٖ��i�V�쐳���j���ɃN���A�ŁA���̃z�[���ɍœK�ȉ����A�ۑ�Ȃ̃C���g���ŋ��܂�\��������X�^�[�g�ł����B����Ȓ��ŁA����̓��j�]���̐��x�ɂ��u�����������ʂ���������A�g���I�����o�^������A�炵����ʕ����������܂������A���|�I�ȉ��y�͂͂���ȍ��ׂȃu�����A�ȒP�ɗ��킵�Ă��܂����悤�ł��B���R�Ȃ͍��N���s��̓V���i�̂ЂƂB���̂���T�E���h�Ƃ���т₩�ȃu���X�T�E���h�͑������Ȃ����y�̐��E�ς����グ�Ă��܂����B���肵���n�[���j�[�Ɛ��x�̍����A���T���u���͂��G��ŁA�����������y�����t�ʼn�����邱�Ǝ��̂ɈӖ��������Ȃ��Ȃ�v���������ł��傤���B���������A�I�[�{�G�̑t�҂������i�K���狃���Ă��܂������A�����������̂ł��傤���E�E�E�E�B |
12: �����x���@�����s��\�@�����s��������O���w�Z �i�w��:�V��N�G�j ���� 2�N�A��11���
�ۑ��3:��VIII-���x�̂��߂̃w�e���t�H�j�[�i�����N�j
���R��:�����i�ۉȗm�j�ۑ�Ȃ́A���ʂɏ�����Ă��鎖����������Ɖ���������ŁA�����B�Ȃ�̉��߂������������G���ł����B��⋭��̕��ɑ���X�s�[�h�����s���߂��̕����������܂������A���x�̍������j�]���Ɗ��ʂ���A���T���u���͔��ɐS�n�悢���E�ς����グ�Ă��܂����B�Ŋy��ƊNJy��̃o�����X���A�T�E���h�ɑ���A�v���[�`���▭�������Ǝv���܂��B���R�Ȃ́A�`���̃��j�]���̐��x�̍����͌����܂ł��Ȃ��A�ׂ����p�b�Z�[�W��Y���̍��ݓ��X�A�������[�ł��̕���ɗՂ�ł��������A���y�Ɖ��t�ɗ]�T���������Ă����悤�ł����B |
13: ���C�x���@���m����\�@���i�s�����i�����w�Z �i�w��:�����q�j ���� ���o��
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:�o���G���y�u���̋R�m�v����iR.�O���G�[���^�ΒÒJ���@�j�o���h�͏��o��ł����A�w���҂͋��N�Ɉ��������Ă̓o��ɂȂ�܂��ˁB�ۑ�Ȃ́A�S�̂�ʂ��ă��Y���̞B���ȕ����┭���̃u��������ꂽ�肵�܂������A�o���L�x�Ȏw���҂Ɉ��������A�����ɂ�������ƕt���Ă������ʂ��ԊJ�����Ƃ��������ł����B���R�Ȃ́A�S�̂̃T�E���h�Ƀ���������ꂽ��A�A���T���u���ɂ����u��������ꂽ��܂������A���グ��ꂽ���y�̗��ꂪ�f���炵���A�ׂ�������������ɗ��킵�Ă��܂����B���㎞�Ԃ������ăT�E���h��肪�Ȃ���čs�����N�́A�X�Ɉ��芴�𑝂��ēo�ꂵ�ė���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ҋ����[���Ɋ��������鉉�t�ł����B
|
1: �k���x���@�ΐ쌧��\�@����s���z���w�Z �i�w��:�|���@���j ��� 3�N�Ԃ�4���
�����3:��VIII-���x�̂��߂̃w�e���t�H�j�[�i�����N�j
���R��:�傢�Ȃ�̑�n�`�`���M�X�E�n�[���i��؉p�j�j�ۑ�Ȃ́A�S�̓I�ɉ��̔������������ȂƂ�����ۂŁA���j�]���̐��x�������ꑧ�������ł��傤���B�܂��A���݊��̂���u���X�T�E���h�ɔ�ׂ�ƁA�؊ǂ̐����ׂ߂Ȃ̂��C�ɂȂ�܂����B���R�Ȃł̓X�e�[�W�Ɋ���Ă����̂��A���������̔������悭�Ȃ�A�Ŋy����܂߂��T�E���h�̃o�����X�����P�������Ă��܂����B����ɁA�[�������A���T���u����W�J���Ă��܂������A���X�Ő�����������Ă��܂��Ă����̂��c�O�ł����B�������A�A�T�C�`�Ƃ����o�����̒��ŁA�o���h�Ƃ��Ă̑��݊����\���ɃA�s�[���������t�������Ǝv���܂��B |
6: �k�C���x���@�D�y�n���\�@�D�y�s���[�����w�Z �i�w��:�c���`�[�j ��� 2�N�Ԃ�4���
�ۑ��4:�}�[�`�u�v�����@���X�̕��v�i�c�Ⓖ���j
���R��:�������g�`�o�b�n�̃J���^�[�^�m�����A�Q���A�J���A�ɂ��n�ƃ��Z���~�T�ȁm�\���˂ɂ����n�̒ʑt�ቹ�ɂ��ϑt���iF.���X�g�^�c�������j�ۑ�Ȃ́A���ɃN���A�ȃT�E���h����ۓI�ŁA��������Ǝ{���ꂽ�A�i���[�[�A�ߕs���Ȃ������������A�����n���̌��������y�͂������Ă��܂����B�S�̂�ʂ��ă����n���̂���D���������Ǝv���܂��B���R�Ȃ��A�����W�̍L���T�E���h���S�n�悭�A���x�̍����A���T���u���ƍ������t�͂��A���y�̏�ʓ]�����X���[�X�ɕ\�����Ă��܂����B����Ȓ��ŁA�X�ɏ�ʂɂ���ăT�E���h�ɂ��ω����o��ƁA���y�ɂ��[�݂��o���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |
8: �����x���@��������\�@�o�_�s�����c���w�Z �i�w��:�Ð�T���j ��� 14�N�Ԃ�5���
�ۑ��3:��VIII-���x�̂��߂̃w�e���t�H�j�[�i�����N�j
���R��:�u���c���z�v �\�Z���`���c�Ղ�`���ړ��A�`����̌��`�z�s�䍰�_�i�V�쐳���j���N�͌ږ�̌Ð�搶�Ō�̔N�������ŁA���̗L�I�̔�������ׂ��A�S�����ɋ��i�߂Ă��܂����B�ۑ�Ȃ́A�����W�̍L���T�E���h�ŁA���̐��E�ς�K�x�ȋْ����Ƌ��ɍ��o���Ă��܂������A���j�]���̐��x�����Â��A���œ_���{�����Ă��܂����悤�ł��B�T�E���h�ɂ�����Ȃ�u�����h�����~���悤�Ɋ����܂����B���R�Ȃ́A�����炭�Ϗ���i���낤�Ǝv���܂����A����̃o���h�̃T�E���h���l�������I�[�P�X�g���[�V���������ɗ킵���A���ɗE�s���������ċ����킽���Ă��܂����B�A���T���u�����A�k���ɑg�ݗ��Ă��Ă��܂������A�Ղ�̏c�̃��Y���ɑ���n�[���j�[���A�X�Ƀ����n�������t���ƁA��i�������яオ�鉉�t�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��������ȂƁA�ɂ��܂�܂��B |
10: �����x���@�����s��\�@�����s��������Z���w�Z �i�w��:���Øa���j ��� 2�N�Ԃ�7���
�ۑ��4:�}�[�`�u�v�����@���X�̕��v�i�c�Ⓖ���j
���R��:���ɂ����̎������iJ.���@���E�f���E���[�X�g�j�ۑ�Ȃ́A���y�̗֊s����������ƍ\�z���ꂽ�D���ł������A�y������n�[���j�[�̓��������U���ŁA����Ȃ�A�i���[�[��A���T���u���̐��x�����߂�A�v���[�`���~���������Ƃ���ł��傤�B�܂������ɋC�������s���߂����̂��A���t�p�[�g���S�̂�ʂ��āA�\��Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂����̂��c�O�ł����B���R�Ȃ́A���̐��E�ς�I�m�ȃA�v���[�`�ŕ\�����Ă��܂������A�S�̂�ʂ��āA���y�I�Ȑ������s���͂��Ă��炸�A�y�Ȃ������Ă��闬��ɂ��C�������Ă������ȂƂ�����ۂł��B�������A�\���y��̏[���Ԃ蓙�A�t�҂̃��x���̍����͂��������j���������o���h���Ȃǎv�킹��ɏ[���������Ǝv���܂��B |
14: �l���x���@��������\�@�����s���{���w�Z���w�Z �i�w��:�ɔ\�����j ��� 2�N�Ԃ�6���
�ۑ��3:��VIII-���x�̂��߂̃w�e���t�H�j�[�i�����N�j
���R��:������1997�u�V�n�l�v�i杏��^�V�쐳���j�_�C�i�~�b�N�ň��芴�̂���T�E���h���������o���h�Ƃ�����ۂł��B�ۑ�Ȃ́A���ɒ��܂�̂���T�E���h�Ɖ��y�����Ă��܂������A���j�]����A���T���u���ɍׂ����u��������ꂽ�̂��c�O�ł����B���R�Ȃ́A�悭�Ȃ�u���X�ƑŊy��̃A���T���u������ۓI�ȉ��t�ł������A�؊ǃT�E���h�Ɍ��݂��o�Ă���ƁA���y�ɕ\���[�݂��o�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�܂��A�S�̂�ʂ��āA�ЂƂ̃T�E���h�J���[�ʼn��y���i��ł��������ŁA�T�E���h�ɑ��l�ȐF�ʊ������߂���Ƃ���ł��傤�B |
2: ��B�x���@����������\�@�������s�����u���w�Z �i�w��:�≺�����j ���� ���o��
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:�̌��u�g�X�J�v����iG.�v�b�`�[�j�^��؉p�j�j�ۑ�Ȃ̃C���g�����X�^�[�g����Ɠ����ɁA�}�C���h�ȃT�E���h���X�e�[�W��ɓW�J����܂������A�S�̂�ʂ��āA���y���q�Ȃ܂œ`����ė��Ȃ����ȂƂ�����ۂł����B���o��Ȃ����ɁA���̃z�[���ł̋����ւ̒����~�X�������ł��傤���B�o�����X�I�ɁA���njn����������Ƌq�Ȃɓ͂���A�v���[�`���~���������Ƃ���ł��B���R�Ȃ͒��J�ɉ��y��a���o���A�؊ǂ̃\����������Ղ�ɉ̂������Ă��܂����B���A�����ł��T�E���h�̃����W�������A���y�̋N�����\��������Ȃ������̂́A�c�O�ł����B |
3: ���k�x���@�H�c����\�@�H�c�s���R�����w�Z �i�w��:�ؓ��@�P�j ���� 5�N�A��34���
�ۑ��4:�}�[�`�u�v�����@���X�̕��v�i�c�Ⓖ���j
���R��:�X�y�C�������Ȃ��A�}���Q�[�j���A�Ղ��iM�����F���^�X�c��_�j�����W�̍L���A�_�C�i�~�b�N�ȃT�E���h�͌��݂ł������A�S�̂�ʂ��āA�A���T���u���̃u�����ڗ����A�����Ő�����������Ă��܂��o�����X�̈������C�ɂȂ�܂����B����Ȓ��ŁA���y�̃����n���̂����͓`�������������܂��B���R�Ȃ́A�S�̓I�Ƀ~�X���ڗ����A���y�̎n�����X���[�X�ɂ������A�S�̂�ʂ��ĎG�R�Ƃ����A���T���u���ɂȂ��Ă��܂��܂����B�s�[�N�̎����čs���������܂������Ȃ������̂����m��܂���B |
9: ���֓��x���@��ʌ���\�@����s���ؒ��w�Z �i�w��:�����T���j ���� ���o��
�ۑ��4:�}�[�`�u�v�����@���X�̕��v�i�c�Ⓖ���j
���R��:�����i�ۉȗm�j�ۑ�Ȃ́A�`�����烊�Y�����d���A�Ŋy��Z�N�V���������肳���������}�[�`�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���y�I�ȐF�t���Ɏ��Ԃ����������Ȃ�y�Ȃł͂���킯�ł����A���̑O�ɁA��{�I�Ȑ����̗���A���Y���̍��ݓ��A�ׂ������y�̗v�f���ЂƂЂƂn���ɐςݏd�˂�n���Ȏ��g�݂���⑫��Ȃ������̂��ȂƂ�����ۂł����B�Ŋy��ƊNJy��̃o�����X�ɂ���l�L��ł��傤�B���R�Ȃ́A�Â��ȋْ��������`���̃��j�]��������s����ȕ����������A�S�̂�ʂ��āA���m���Ŗ{�Ԃ��}���Ă��܂����悤�ł����B��{�I�ȃT�E���h�≉�t�͂͂���o���h�Ȃ̂ŁA����Ɋ��҂������Ƃ���ł��B
|
11: ���C�x���@���m����\�@���É��s���_�u���w�Z �i�w��:���썎�F�j ���� 2�N�Ԃ�2���
�ۑ��1 �V��̗��|���t�y�̂��߂�李��|�i�Ό��E���Y�j
���R��:�G�j�O�}�ϑt���iE.�G���K�[�^���{�K��j���N�̑S�����B��ƂȂ����ۑ��1�ԁB�S�̂�ʂ��āA�T�E���h���������ȂƂ�����ۂł������A�y�Ȃ̃I�[�P�X�g���[�V�����ɂ�镔�����傫�����������m��܂���B�����A�S�̂�ʂ��Ĕ������B���Ȋy�킪�U������A���y�̃��C�����{�����Ă��܂����̂��c�O�ł����B���ԕ����́A�����Ƒΐ����̃o�����X���A�ׂ����z�������߂���Ƃ���ł��傤�B���R�Ȃ́A�T�E���h�ɂ������������A���̐��E�ς�I�m�ɕ\�����Ă��܂����B�����A��╈�ʂɗ����ꂷ���Ă��镔��������ꂽ�̂������ŁA������Ă��镔���������y�I�ȑi�����A���̎���̒��w�̕��ɂ͋��߂��n�߂Ă��鎖���c������ׂ��ł��傤�B |
15: ���k�x���@�R�`����\�@�R�`�s����O���w�Z �i�w��:�Έ�@�ρj ���� 10�N�Ԃ�5���
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:�����Ȃ���i���H�Y�^���{���l�j�ۑ�Ȃ́A�C���g������t���[�Y���ɕs���R�ȕ����������A���j�]�������肵�Ȃ����炩�A�����̏œ_���u���Ă��܂��������ł����B���邢�T�E���h�������Ă��邾���ɁA�A�i���[�[�s�����ۂ߂Ȃ������ł����B���R�Ȃ́A�����̃u�����U������A���y���G�ɒ������Ă��܂�����ۂł����B�܂��A�}�g�̕ω����R�����A�S�̂�ʂ��ĉ��y�����R�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂����悤�ł��B���ʂɂ��鋭�ゾ���łȂ��A����̒��Ŋ�����}�g�����y�ɔ��f������̂��A�厖�ȃA�v���[�`�̂ЂƂł͂Ȃ��ł��傤���B |
 |
6: ���C�x���@������\�@�l���s���J�����w�Z �i�w��:�����K���Y�j ���� 3�N�A��3���
�ۑ��4:�}�[�`�u�v�����@���X�̕��v�i�c�Ⓖ���j
���R��:�o���G���y�u�V�o�̏����x���L�X�v���A��1.2.4�y���iO.���X�s�[�M�^���c���j�ۑ�Ȃ̃C���g���́A�ł�����悤�Ȕj���v�����@���X�̏�i�̍Č��ɐ��������Ă��܂��������������̂��c�O�ł������A���̌�̓W�J�͎��������A�A���T���u���͂̍����A�������ۗ������쉢���}�[�`�����������Ă��܂����B�����Ŋy��Ƃ̃o�����X�������A���ɑe�G�ȉ��y�ɂȂ��Ă��܂����̂͐ɂ����Ƃ���ł��B���R�Ȃ͔��ɍ������t�͂��ւ��������ł����B���j�]���̐��x���f���炵�������̂ł����A�T�E���h�Ƀu�����h�����o��ƁA�X�ɉ��y�ɐF�ʊ�������������ł��傤�B�S�̂�ʂ��āA���̃z�[���ɂ����Ă͉����ߑ������������m��܂��A���̕��L�������W���������T�E���h���A���y�Ƀ����n����t����̂ɐ��������悤�ł��B |
11: �k�C���x���@���ْn���\�@�k�l�s����钆�w�Z �i�w��:�����~��j ���� 2�N�Ԃ�2���
�ۑ��3:��VIII-���x�̂��߂̃w�e���t�H�j�[�i�����N�j
���R��:���C�E�u�[�W�����[�̎]���̂ɂ��ϑt���iC.T.�X�~�X�j�ۑ�Ȃ̑O���́A�N���̃T�E���h���ׂ߂Ȃ̂��C�ɂȂ�܂������A���X�ɃT�E���h�Ɍ��݂������A�t�ɃI�[�v�j���O�ƏI�Ղ̃R���g���X�g�����ʓI�ɍۗ����o�ɂȂ�܂����B�S�̂�ʂ��ăA�i���[�[����������Ǝ{���ꂽ�D���ŁA�A���T���u���̐��x�����ɍ����A��풾���ȑŊy��Q���A���y�ɐ[�݂������炵�Ă��܂����B���R�Ȃ̓T�E���h����ς��A�N���[�h�E�X�~�X�̐��E�ς��[���ɍČ����������ɂȂ�܂����B���x�̍����A���T���u���A�d���ȃR���[���A�I�[�{�G���\���y��̃��x���̍����A�X�~�X�̊y�Ȃŋ��߂���z�����̏[���Ԃ蓙�X�A��C�ɋq�Ȃ̋�C����ς��Ă��܂����̂悤�ȁA�ڂ̊o�߂�G���������Ǝv���܂��B�����ĉ��������y�������Ă����̂��A�D��ۂł����B |
12: ���֓��x���@��ʌ���\�@�����s��������ꒆ�w�Z �i�w��:�O���O�g�j ���� ���o��
�ۑ��3:��VIII-���x�̂��߂̃w�e���t�H�j�[�i�����N�j
���R��:�̌��u�g�D�[�����h�b�g�v����i�f.�v�b�`�[�j�^�㓡�m�j�s�p�I�ŃN���A�ȃT�E���h�́A���̉ۑ�Ȃɔ��Ƀ}�b�`�������̂ŁA�����A�i���[�[�͂̉��A���x�̍������j�]����u���̖����A���T���u�����A�y�Ȃɑ�����^���Ă����悤�ł����B�Ŋy��̃X�L�����������x���������Ǝv���܂��B�S�̂̃T�E���h�ɍX�Ƀu�����h���������A���y�ɐ[�݂��o���̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂������A������w���Ƃ��Ă͏[���Ƀ��x���̍������y�����������Ă����Ǝv���܂��B���R�Ȃɂ����Ă��A�����W�̍L���T�E���h�A�\���y��̏[���x�A���肵���n�[���j�[���X�A���x�̍������t�ŁA�y�Ȃ����X�g�[���[���A�F�ʊ��������čČ����Ă����̂ɁA�������܂����B |
13: �����x���@�����s��\�@�H���s���H����ꒆ�w�Z �i�w��:�ʊ��j ���� 2�N�Ԃ�8���
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:�V���ٖ��i�V�쐳���j�d���ł���т₩�ȃT�E���h�ŃX�^�[�g�����ۑ�Ȃ́A���������߂̃e���|�ݒ�ł������A���肵���n�[���j�[���S�n�悢�D���ł����B�g���I�̃`���[�o���A��┭���Ƀu��������ꂽ����������܂������A�ߕs���Ȃ����y�̗v�f���a����Ă��������ŁA�Ŋy��̊���Ԃ���f���炵���}�[�`�ł����B���R�Ȃ̓y�b�g3�Z��̊�����f���炵���A�[�������A���T���u���ƁA���x�̍������j�]������������Ɖ��y���x���A�����ł��p�[�J�b�V�����Q�̊���͂������B�܂��ɕό����݂ɉ��y���t�ł��Ă����̂ɒE�X�ł����B
|
2: ��B�x���@��������\�@�����s���Õl���w�Z���w�Z �i�w��:�{�{�@���j ��� ���o��
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��::���b�L�[�h���S���`��ܕ����ۂ̋L���i�����O�a�j�����W�̍L���T�E���h���S�n�悢�ۑ�Ȃ́A��������Ɛ������Č�����A�����n���̌����������̃}�[�`�����Ă���܂����B�����Ńn�[���j�[�ɂ������ꂽ�̂��c�O�������ł��傤���B���R�Ȃ́A���j�]���̐��x���Â��A�A���T���u�����G�R�Ƃ��Ă��āA���ْ����̔��������y�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�I�[�{�G�̃\�����A�t�ҌX�̉��t�͍͂������̂����������܂������A����Ȃ鉹�y�I�Ȑ������{���Ăق��������Ƃ���ł��B |
3: ���֓��x���@��t����\�@���ˎs����ꒆ�w�Z �i�w��:���؍K�G�j ��� 2�N�A��2���
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:�E�C���h�I�[�P�X�g���̂��߂̃}�C���h�X�P�[�v�i�� �����j�O�����������A�X�ɃT�E���h�I�ɂ����t�͓I�ɂ����x���A�b�v���Ă����̂���ۓI�ȉۑ�Ȃ̃X�^�[�g�ł����B�N���A�Ń����W�̍L���T�E���h�͔��ɐS�n�悭�A�A�i���[�[����������Ǝ{���ꂽ�D���ł��B����Ȓ��ŁA�X�l�A�����x��铙�A�A���T���u���̃u�����U�����ꂽ�̂��c�O�B�T�E���h�I�ɂ��ቹ�y��Ƀu�����h�����o��ƁA���y���X�Ɉ��肵�����Ƃł��傤�B���R�Ȃ́A�S�[�W���X�ȃT�E���h�A�\���y��̔������A���j�]���̐��x�̍����A�����ĐF�ʖL���ȉ��y��肪�ۗ������ł����B�S�̂�ʂ��āA�X�L�̖������t�͂̍������ւ��Ă��܂������A�����ł��X�Ȃ�T�E���h�̃u�����h�����~���������Ƃ���ł��B |
7: ���x���@���Ɍ���\�@��ˎs�����R�܌��䒆�w�Z �i�w��:�n�ӏG�V�j ��� 3�N�A��12���
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:���t�y�̂��߂̕��i���u�z������Ƃ��v����i�� �����j�o�����X�̂����T�E���h�ɂ��C���g������X�^�[�g�����ۑ�Ȃł������A�����ɂ����郊�Y���Z�N�V�����ɂ��o�^�c�L������ꂽ�̂��c�O�ł����B�܂��A�g���I�ɂ����Ă͒ቹ�y�킪���肹���A�g���I�J���̃P�A���X�~�X���ɂ��������Ƃ���ł��B�������A�S�̂�ʂ��Đ������悭���������A�D���������Ǝv���܂��B���R�Ȃ́A�ӂ��悩�ȃT�E���h�̖؊ǂ��S�n�悭�A���肵���n�[���j�[�A�����������A�����ău�����h���̂悢�T�E���h���S�n�悢�A�����x�̍������y�����Ă���܂����B����Ȓ��ŁA�J�b�g�ɂ��s���R���������Ă��܂��܂������E�E�E�E�B |
9: ���x���@���Ɍ���\�@�L���s����\�ꒆ�w�Z �i�w��:���{�T�s�j ��� 3�N�Ԃ�4���
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:���ɂ̔g���i�����~�j�ۑ�Ȃ̃C���g���͂�������Ƃ�����ۂŁA�����̃��j�]���̐��x���Â߂������ł��傤���B�T�E���h��n�[���j�[���S�̓I�ɕs����ŁA�g���I�ł̒ቹ�̃u�������ڗ����Ă��܂��܂����B�����n���ɂ��������A���s�{�ӂȉ��t�������̂ł͂Ƒz�����܂��B���R�Ȃł́A�X�̑t�҂̉��t�͂������Ă��܂������A���ʉ����o�����X�I�ɉߑ��ŁA�œ_�̃{���������y�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�A�i���[�[�����ƈ���̈�ۂŁA���y���������Ȃ������̂��c�O�ł����B |
10:��B�x���@�F�{����\�@�V���s���{�n���w�Z �i�w��:�����ؐm�j ��� ���o��
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:�����ȑ�R�Ԃ��A��1,3,4�y���iJ.�o�[���Y�j�}�C���h�ȃT�E���h�ŃX�^�[�g�����ۑ�Ȃł����A�t���[�Y���ɂ��s���R���������鉉�t�ŁA�A���T���u���ɂ������ȃu���������Ă��܂����B���y�̗���Ƃ��Ă��A�������ɂ͌����Ă��܂��܂������A���J�ɉ��y���g�ݗ��Ă��Ă����͍̂D��ۂł����B���R�Ȃ́A�S�[�W���X�ȃT�E���h������4�y�͂Ō����Ă��܂������A���njn�̉������X�Ɋ�������ƁA���y����藧�̓I�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����Ő�����������Ă��܂����̂��c�O�ł����B |
14: ���֓��x���@�_�ސ쌧��\�@���l�s���{�����w�Z �i�w��:��������j ��� 2�N�Ԃ�2���
�ۑ��3:��VIII-���x�̂��߂̃w�e���t�H�j�[�i�����N�j
���R��:�n���\���̖��iP.�O���n���j��������ƃA�i���[�[���{���ꂽ�ۑ�Ȃ́A�����W�̍L���T�E���h�A�[�������A���T���u���A�ӂ��悩�ȃT�E���h�̃��j�]�����X�A���֓��̒��w�Z�̃��x���̍�������������悤�ȍD���ł����B�p�[�J�b�V�����̊�����f���炵�������̂ł����A�S�̂�ʂ��Ă����S�^�]�Ӗ��ŁA���y�����܂ЂƂm���炸�ɒʂ�߂��čs���Ă��܂����̂��c�O�������ł��傤���B���R�Ȃ́A�k���ɗ���ꂽ���y��W�J���Ă����̂���ۓI�ŁA��t�ɂ�����n�[���j�[�̈��芴�����̃o���h�̒�͂��������Ă��܂����B����Ȓ��ŁA�o�����X�I�Ƀp�[�J�b�V��������⋭�߂��������߁A�ׂ����t���[�Y��������Ă��܂���ʂ�����ꂽ�̂��c�O�ł����B |
15: �����x���@�R������\�@�h�{�s���K�R���w�Z �i�w��:���T��Y�j ��� 4�N�A��11���
�ۑ��4:�}�[�`�u�v�����@���X�̕��v�i�c�Ⓖ���j
���R��:�M���`���l�T���X�̌���i��؉p�j�j�m�����̎w���҂́A���N�܂Ŗh�{�����Z���w�����Ă����Ǝv���܂����A���̉e�����T�E���h���S�̓I�ɑ�l�̋����ɂȂ������ȂƂ�����ۂ������܂����B��������ƃA�i���[�[���ꂽ�ۑ�Ȃ́A��������������ƕ�������D���ŁA�������ɂ܂Ŕz���̍s���͂������y�̐ςݏd�˂����ɐS�n�悩�����Ǝv���܂��B���R�Ȃ��S�[�W���X�ȃT�E���h�ƁA���x�̍������j�]�����A���y�𗧑̓I�ɍ\�z����̂ɐ��������Ă��܂������A���̐��E�ς̌������ɂ͐����������̂́A���y���̂��̂���▟�R�Ƃ��Ă��܂��Ă����̂��c�O�ł����B |
1: �k���x���@���䌧��\�@���s���O�����w�Z �i�w��:����@�W�j ���� 2�N�A��2���
�ۑ��4:�}�[�`�u�v�����@���X�̕��v�i�c�Ⓖ���j
���R��:�t�F�X�e�B�o���E���@���G�[�V�����iC.T.�X�~�X�j����悭�����W�̍L���T�E���h�ŃX�^�[�g�����ۑ�Ȃ́A�������ۗ��A�����n���̕t�����D���ł����B��⒆���悪�ׂ߂��ȂƂ�����ۂ������̂ƁA�~�X�g�[�����U�����ꂽ�̂��c�O�ł����B���R�Ȃ́A���N�ɑ����ăN���[�h�E�X�~�X��i�ł������A���̋Ȃ͓��Ƀz���������w���ɂ͓�����������m��܂���B����Ȓ��ł��A�s�b�R����t�@�S�b�g���A�؊NJy��̃\���̐��x�͍����A�S�̂̃A���T���u���́A���y�̏�ʍ��̏�肳�͍ۗ����̂����������Ă��܂����B���N�͂ǂ�ȃ`�������W�������Ă����̂��A�y���݂ł��B |
4: ���k�x���@��茧��\�@�k��s����쒆�w�Z �i�w��:�`�D�j ���� ���o��
�ۑ��3:��VIII-���x�̂��߂̃w�e���t�H�j�[�i�����N�j
���R��:�o���G���y�u�����̌v����iP.�`���C�R�t�X�L�[�^�ۉȗm�j�����I�ɂ͗]�T���������T�E���h�Ƃ�����ۂł������A�A�i���[�[�s�����͔ۂ߂��A���y�����R�Ɛi��ł����Ƃ�������ۂ������͎̂c�O�ł����B�T�E���h�̃o�����X�ɂ��čl�̗]�n�����肻���ł��B���R�Ȃł́A���j�]���̐��x�̍����͊������܂������A���̏o�����������ɑ���Ȃ�������A�g�D�b�e�B�ł͐�����������Ă��܂����A���y�I�Ȑ������X�Ɏ{���K�v�����������鉉�t�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�܂���ʂ��ƂɁA���y�̐F��ς��Ă����H�v���A���������y�Ȃ̏ꍇ�͕K�v�ɂȂ��Ă��鎖�ł��傤�B |
5: ���֓��x���@��ʌ���\�@�z�J�s���告�͒��w�Z �i�w��:�c���G�a�j ���� 2�N�A��2���
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:�̌��u�g�X�J�v����i�f.�v�b�`�[�j�^�㓡�m�A�c���G�a�j�S�̓I�Ƀo�����X�̂悢�A�����W�̍L���T�E���h�͌��݂ł����B���A�ۑ�Ȗ`���A���̃N���̐����ׂ��A�n�[���j�[�����s����ŁA���̎w���҂̉��y���Ƃ��Ă͈ӊO�ȓW�J�ɂȂ��Ă��܂����B�g���I�ł��ቹ�y���~���[�g�y��Ƀ~�X���U������铙�A��⒲���Ɏ��s���Ă��܂������ȂƂ�����ۂł����B�I�Ղ͑ΐ����Ƃ̃o�����X�ɂ����ӂ��K�v�ł��B���R�Ȃ́A�Ŋy��{�[�C�Y�̊��ڗ����Ă��܂����B�������A�����ł��NJy��̃n�[���j�[�����肹���A���j�]���ɂ��u�����ڗ��ȂǁA�S�̓I�Ƀ����n�������������y�ɂȂ��Ă��܂����̂��c�O�ł����B |
8: �l���x���@���Q����\�@���R�s����쒆�w�Z���w�Z �i�w��:�O���D�q�j ���� 36�N�Ԃ�4���
�ۑ��2:�}�[�`�u�t�̓����s�����v�i�����M�G�j
���R��:���t�y�̂��߂̕��i���u�z������Ƃ��v����i�� �����j�����������O�̒��w�Z�̓o��ł��B�ۑ�Ȃ͑S�̂�ʂ��āA�A�i���[�[�����r���[�ŁA�T�E���h�̃o�����X��u�����h�������܂ЂƂƂ�����ۂł����B�����̃N���̃��j�]���A�g���I���O�̃g�����{�[���̏������A�R���N�[���Ƃ�����ő��Ɣ�r����₷�������ւ̔z�����s�����Ă����悤�ł��B����Ȓ��ŁA�Ŋy��̊��ڗ����Ă��܂����B���R�Ȃ́A���t�͂��\���ɔ������Ă��܂������A���������ߑ��Ȉ�ۂ������̂ƁA�S�̓I�ɐ��������ڂ����A�����Ő�����������Ă��܂����t�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�ǂ���������������H�I�ȉ��y�A�Ƃ�����ۂ������ł��傤���B |